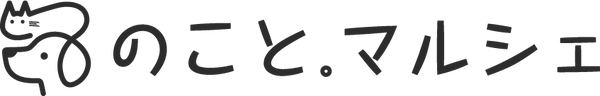甘い香りにつられて、つい猫があんこに興味を示す…そんな経験はありませんか?実際に猫にあんこを食べさせて良いのか迷う飼い主さんも多いでしょう。本記事では、猫とあんこの関係について解説します。安全にあげるためのポイントや、猫が好む理由、代替おやつまで詳しく紹介します。
猫はあんこを食べても大丈夫?【砂糖抜きで少量ならOK】

基本的に、猫にとってあんこは「ごはん」とは言えませんが、少量であれば危険な食べ物ではありません。
ただし、それはあくまで「砂糖や添加物を含まない、純粋な小豆を炊いたあんこ」に限ります。一般的な市販のあんこには、砂糖がたっぷりと使われており、猫の健康には適しません。
猫は糖分を分解・代謝する能力が低いため、糖分の多いものを摂取すると肥満や糖尿病、膵炎などのリスクが高まります。
たとえ一口でも、砂糖入りのあんこを頻繁に与えるのは避けてください。
どうしてもあげたい場合は、甘味料を使っていない無糖あんこを、ほんの少量だけ与えるようにしましょう。
猫はあんこを使った加工品を食べても大丈夫?【大福、どら焼き、羊羹(ようかん)など】

大福やどら焼き、羊羹などの和菓子には、小豆以外にもさまざまな材料が使われています。砂糖はもちろん、バターや油脂類、小麦粉、保存料などが含まれていることが多く、猫にとっては消化に負担がかかるうえ、アレルギーを引き起こす可能性もあります。
特に羊羹は砂糖の含有量が非常に高く、粘度も高いため、猫の喉や消化器に詰まる危険性も。
また、大福の餅部分は粘着性が強く、猫が誤って大量に口にしてしまうと窒息のリスクも否定できません。
このように、あんこを含む加工品は猫の体にとって有害な成分が含まれていることが多いため、与えるのは控えましょう。猫が欲しがっても、人間用のおやつは「絶対にあげない」と決めておくのが安全です。
あんこ(小豆)に含まれる栄養素とその効果

小豆は、ヒトにとっては栄養価が高く、さまざまな健康効果が期待される食品です。しかし、猫は本来肉食動物ですので、小豆は「メインの栄養源」にはなり得ないということを理解しておくことが大切です。主な栄養素は以下の通りです。
食物繊維
小豆には豊富な食物繊維が含まれており、腸内環境を整える作用があります。人間にとっては便秘予防や腸内フローラの改善に有効ですが、猫は本来、食物繊維を人間ほど多く必要としない動物です。摂りすぎると消化不良や下痢の原因になるため、注意が必要です。特に皮に多く含まれるため、与える際は工夫をしましょう。
鉄分
鉄分は赤血球の生成に関わる重要なミネラルで、小豆にはこの鉄分も含まれています。猫にとっても鉄分は必須の栄養素です。しかし、植物性由来の鉄分は吸収効率が悪いため、貧血予防を目的とするなら動物性の鉄分を含む食材のほうが適しています。
ポリフェノール
小豆の赤い皮に含まれるポリフェノールは、強い抗酸化作用を持ち、老化予防や免疫力の維持に役立つ成分として知られています。猫に対しても理論上はメリットがありますが、吸収性や効果についてはまだ研究段階です。
植物性たんぱく質
小豆には植物性たんぱく質が多く含まれており、筋肉や臓器の維持に必要な栄養素です。ただし、猫は動物性たんぱく質を主に必要とする肉食動物であり、植物性たんぱく質だけでは必須アミノ酸のバランスが不十分です。小豆を主食やたんぱく源として与えるのは適していません。
猫にあんこを与える際の注意点
猫にあんこを与える際には、いくつかの大切なポイントがあります。
砂糖抜きのあんこをあげる

猫に与えるあんこは、必ず「砂糖を使っていないもの」を選んでください。一般的な市販のあんこは、猫の体には有害なほど糖分が多く含まれています。猫は糖を代謝する力が弱く、肥満・糖尿病・膵炎などの原因になるおそれがあります。手作りで砂糖を使わずに炊いたあんこなら、少量であれば比較的安全です。
少量をあげて様子を見る

猫によっては小豆に対する体の反応が異なります。食物繊維やサポニンといった成分に敏感な猫は、あんこを食べることで下痢や嘔吐を起こすこともあります。初めて与える際は、ごく少量にとどめ、24時間以内の体調の変化を注意深く観察しましょう。少しでも異常があれば、それ以上は与えず、獣医師に相談するのが安心です。
あんこをおやつとして常用しない

あんこは猫にとって「栄養補助食品」ではなく、「嗜好品」に分類されます。いくら無糖・無添加でも、あんこを日常的に与えるのは栄養バランスの乱れにつながります。また、あんこを好む猫の場合、そればかりを欲しがるようになる可能性もあるため、あくまで「たまに与える特別なおやつ」としてとどめておくのが理想的です。
猫にあんこをあげる際、おすすめの食べさせ方

猫にあんこをあげる際は、日常的に与えるのではなく、あくまで「ご褒美」や「特別な日」の選択肢として考えるとよいでしょう。安全に与えるために以下のような方法をおすすめします。
指先に少量のあんこを乗せて与える
初めて猫にあんこを与える場合は、無糖の小豆ペーストをほんの少量、飼い主の指先にのせて舐めさせる方法がおすすめです。猫はにおいと味にとても敏感なので、自分のペースで確認しながら食べられるこの方法は安心です。無理に口元に持っていかず、猫が自発的に近づいてくるのを待ちましょう。
総合栄養食にごく少量混ぜて与える
日常的に食べている総合栄養食のウェットフードや手作りごはんに、無糖の小豆ペーストを耳かき1杯ほど混ぜて与える方法もあります。香りがほんのり加わることで猫の食欲が刺激され、食事に変化をつけることができます。あくまで香りづけや特別感を演出する程度にとどめるのがポイントで、あんこを主成分にしないことが大切です。
猫が誤って、あんこ(砂糖入り)を食べてしまった場合の対処法
目を離したすきに猫が砂糖入りのあんこを食べてしまった…。そんなときは、まず落ち着いて状況を確認しましょう。少量(小豆ひと粒程度)であれば、すぐに症状が出ることは少ないですが、様子見は必要です。
次のような症状が見られた場合は、早めに動物病院を受診してください。
- 嘔吐・下痢
- 元気消失
- 呼吸が荒い
- けいれん
猫がいつ、どれだけの量を食べたのか、どのような製品だったか(成分表示など)を把握しておくと、獣医師による診断がスムーズになります。念のため、商品のパッケージを写真に撮っておきましょう。
あんこが好きな猫もいる!その理由は?

「猫があんこの匂いを嗅いで、うっとりした顔をしていた」「あんこを舐めたがる猫」「あずきの匂いが好きな猫」という話はよく聞きます。
実は、匂いが理由の一つです。小豆の香りには、猫の嗜好性をくすぐるような香ばしさや甘さが含まれていると考えられています。特に、火を通した穀物や豆の香りは、猫が興味を示しやすい傾向があります。
また、猫は好奇心が強く、目新しいものに惹かれる子や、飼い主が食べているものに興味を持つという子が多いということも理由の一つです。興味を示すからといって、頻繁に与えるのは避けましょう。
小豆を茹でて、そのまま猫に与えても大丈夫?

砂糖や塩などを加えずに、小豆を茹でただけの状態であれば、猫に少量与えるのは比較的安全です。ただし、小豆の皮には食物繊維が多く含まれており、量によっては消化にあまり良くありません。猫によっては未消化のまま便に混じって出てくることもあります。
また、猫の腸内環境によっては、食物繊維に過剰に反応して軟便や下痢を起こすこともあるため、与える量と頻度には注意しましょう。はじめて与える場合は、皮を軽く取り除く、または潰して与えることで消化を助けることができます。
【獣医師からアドバイス】あんこに代わる、猫におすすめのおやつ
あんこの代わりに、もっと猫の体にやさしく、楽しめるおやつを選んでみましょう。以下のような食品が、猫にとってはより適したご褒美になります。
- 茹でた鶏むね肉(味付けなし)
- 無添加のフリーズドライささみ
- 猫用の無添加ゼリーやスープ
- 市販の猫用おやつで原材料がシンプルなもの
あくまで「おやつ」であり、主食とは分けて考えることが大切です。体重管理や持病がある猫には、必ず獣医師と相談のうえ、与えるようにしましょう。
▼猫のおやつをお探しの方におすすめなのが、犬猫用ゼリー「ジュレッタ」です。
いつものフードに添えて与えるだけで、必要な水分量を摂取できます。「チキン」「かつお」「ヤギミルク」「タイ」など、豊富なフレーバーが用意してあるのでおいしく水分補給できます。香料、保存料、人工着色料は一切使用していない無添加の安全なおやつです。
まとめ
猫はあんこや小豆に興味を示すことがありますが、与える場合は「無糖・無添加・ごく少量」が鉄則です。市販のあんこや加工和菓子は、基本的に猫には不向きであり、避けるべき食品です。猫の健康を守るためにも、嗜好性に頼らず、栄養的にも安心なおやつを選んであげましょう。
あんこを安全に楽しむには、飼い主さんの正しい知識と注意が欠かせません。万が一、誤食してしまった場合も慌てず、冷静に対処し、心配な場合は獣医師に相談しましょう。
監修の獣医師プロフィール