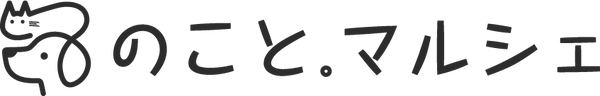「愛犬がなかなかお水を飲んでくれない」と悩む飼い主さんに、原因と対処法を獣医師が説明します。
ゼリー・スープ・ウェットフードなど目的に合わせて使えるおすすめ5選も解説します。
ぜひ最後までお読みいただき、無理なく愛犬の水分摂取量を増やすヒントにしてください。
※本記事は犬を中心に解説していますが、犬猫共通の水分補給の考え方や選択肢をまとめています。
犬の水分補給におすすめの方法・グッズまとめ

愛犬がなかなかお水を十分に飲んでくれないとお悩みの飼い主さんに、おすすめの対処法をご紹介します。 ゼリーやスープ、ウェットフードなど、暮らしの中で無理なく続けられる工夫を中心にまとめました。
① 食べておいしい水分補給ゼリー
まずおすすめしたいのが、犬用ゼリーです。
愛犬が水をなかなか飲まなくても、香りと食感が好みだと自発的に口にしてくれることがあります。
食事と一緒に“食べる水分”として与えることができるため、1日の総水分量をしっかりと確保しやすいのが利点です。
手作り派は、無糖の出汁とゼラチン・寒天でも作れますが、甘味料や塩分の入りすぎには注意してください。
水に溶かして冷やすだけで作れるため、いつものフードに添えて与えるだけで、必要な水分量を摂取できます。香料、保存料、人工着色料は一切使用していない添加物不使用の安全なおやつです。
② 香りで誘うスープタイプ(ヤギミルク・野菜スープなど)
ゼリーが難しい場合はスープとして水分補給させてあげることも良いでしょう。
香り立ちの良い野菜の出汁や犬用ヤギミルクをぬるめにしてあげると、最初の一口を後押しできます。
一度「おいしく飲めた」経験があると、犬は味や香りを覚えて、食事や休憩のたびに抵抗なく口をつけてくれやすくなります。
ミルク系では、定番のヤギミルクに加えて、【ニュージーランド産】ひつじミルク(犬猫用)もおすすめです。
やさしい甘みと自然な香りで、食欲が落ちているときでも口にしやすい味わいです。
スープ派には、【国産・無添加】犬猫用ジビエで作ったスープの素(鹿/猪)も人気です。
鹿と猪それぞれの風味を活かし、香りと栄養のバランスにこだわった無添加仕上げのため、老犬(高齢犬・シニア犬)にもおすすめできます。
食事に少量混ぜたり、フードのトッピングにしたりして、水分補給のバリエーションを増やしてあげましょう。
味が濃いものや人間用のスープは塩分が多いため、必ず犬用・無添加タイプを選ぶと安心です。
③持ち歩きやすい給水ボトル&カップ
外出時の水分補給は、出してすぐ飲ませられるカップ付き携帯ボトルを常備するのが最も確実です。
散歩や外出の合間にサッと飲ませられるので、暑い日や興奮しやすい場面の脱水対策に役立ちます。
ボトル一体型カップや折りたたみボウルをバッグに常備し、出発前後にもひと口ずつ与えるこまめな習慣をつけましょう。
④老犬にもやさしい無添加ウェットフード
老犬(高齢犬・シニア犬)の水分補給には、無添加ウェットフードをおすすめすることが多いです。
ウェットフードは、犬にとって嗜好性の高いにおいで、噛む力が落ちた老犬でも食べやすい形状です。
いつもの食事に混ぜるか一部を置き換えると、無理なく水分摂取が底上げできます。 持病がある場合は、かかりつけ獣医師の食事指示に沿って選ぶと安心です。
⑤体調や季節に合わせた水分補給サプリ
犬用の風味づけパウダーや電解質サポートの補助サプリで、”飲み始め”を助けると効率的です。
基本は水・ゼリー・スープで土台を作り、必要なときだけサプリで微調整する考え方が続けやすいでしょう。表示を確認し、犬用として設計された製品を選びましょう。
ポイント
ゼリーやスープ、ウェットフードやサプリを使って、においや食感を工夫できます。自ら水分摂取させることを目標にしましょう。
なぜ犬に水分補給が大切なの?

「最近愛犬があまり水を飲まない気がする…」と不安になっていませんか?
そもそもなぜ水分補給が大切なのか、どんな時に水を飲ませた方がいいのか、必要な水分量はどのくらいなのかを解説します。
犬の体の約6割は水分!生命維持の要
水分は、体温を整え、血液をめぐらせ、食べ物の栄養を運び、体にとって不要なものを尿と便で出すために欠かせません。
まさに生命維持の要です。
犬の体は約6割が水分でできており、“からだの主役”とも言えます。
水を飲む量が不足すると、体の負担が積み重なり、腎臓や膀胱・その他臓器への負担が進みます。
少しずつでも毎日続けて補給できる形を整えることが大切です。
脱水症状のサインと見分け方
以下の項目が脱水のサインとして知られています。
- 口の中:歯ぐきが乾く・ねばつく、舌が乾く/糸を引く唾液
- 目:落ちくぼむ、涙が少ない・目やに増加
- 尿:量が減る、色が濃い、間隔があく
- 行動:元気・食欲低下、ぐったり、心拍・呼吸が速い、過度のパンティング
- 皮膚:首や背中のつまんだ皮膚が戻りにくい
- 体:体温の上下、四肢が冷たい
自宅でチェックできる簡単な見分け方は以下の通りです。
- ・口腔粘膜
- 歯ぐきを指でこすり、しっとり→正常
乾燥・ベタつき→脱水の可能性 - ・毛細血管再充満時間(CRT)
- 歯ぐきを1秒押して離し、ピンクに戻るまで「≦2秒が目安」「>2秒」は脱水の疑い。
- ・スキンテント(皮膚つまみ)
- 首の皮膚を軽くつまんで離し、1秒以内に戻るのが目安。遅いほど脱水を疑う。(高齢犬、肥満、皮膚がたるみやすい犬種ではスキンテントは不正確になりやすい)
- ・尿とうんち
- 尿が極端に少ない・濃い/下痢や嘔吐が続く→脱水リスクが高い。
- ・体重
- 短期間での体重減少(数%)は水分喪失を示すことがある。
注意点
脱水症状が出る前から、水分不足は始まっています。
上記のサインや見分け方が、すべて水分不足が原因と断定できるわけではありません。
私たち獣医師も、これらは参考程度に確認しています。
1日に必要な水分量の目安
基本の目安は体重×約50〜60mL/日です。
| 犬の体重 | 1日に必要な水分量目安 |
|---|---|
| 5kg | 約250〜300mL |
| 10kg | 約500〜600mL |
暑い日・運動量が多い日・授乳期・持病がある場合は必要量が増えやすいので、少し多めを意識しましょう。
急に極端な増減が続くときは、早めに獣医師へご相談いただくと安心です。
犬が水を飲まない主な原因

「どうして水を飲まないの?」という疑問の答えは、体のこと・暮らし方・季節など、いくつかの要因が重なっていることが多いです。
大きく分けて次の3つをチェックすると、原因の見当がつきやすくなります。
体調・病気・ストレス・加齢の影響
体の不調や気分の変化、年齢に伴う変化があると、水を口に運ぶ意欲が下がりやすくなります。
また、口内炎・歯の痛み、吐き気や下痢、腎泌尿器や内分泌の持病、発熱や痛み、環境変化のストレスなどが積み重なって飲水が落ちることがあります。
嗅覚や味の感度が下がるシニア期では「飲みたい」と感じにくいだけでなく、関節痛でお水のある器まで行くこと自体が負担になる場合もあります。
ぐったりする、急な食欲低下や嘔吐・下痢が続くなどの異変があれば、早めの受診をご検討ください。
食事からの水分が多く、喉が渇きにくい場合も
ウェットフードやスープ、ゼリーを取り入れていると、見かけの飲水量が少なくても総水分量は満たしていることがあります。
缶・パウチなどのウェットフードは水分が多く、食事の段階でしっかり水分を取り込めているコは、器の水をあまり減らしません。
うんちが硬すぎない、尿の色や回数がいつも通り、元気と食欲が保たれているなら、現状は大きな問題がない可能性があります。
持病がある場合は、かかりつけ獣医師の指示に合わせて量と与え方を調整してください。
寒い季節・器の形・水の温度も関係
季節や飲む環境が合わないと、水に口をつけにくくなることがあります。
寒い時期は喉の渇きを感じにくく、冷たすぎる水や金属臭・塩素臭、深すぎる器や滑る床、器の高さの不一致も、水分補給を避ける理由になってしまいます。
ぬるめの温度にする、陶器や樹脂など好みの器へ変える、複数の場所に浅めの器を置く、足元にマットを敷いて安定させるといった小さな工夫で、飲みやすさが改善します。
ポイント
基本的には、人間が水を飲もうとする状況や環境は、犬も同じだと考えて差し支えありません。そう考えると、それぞれの暮らしの状況に合わせて工夫しやすいですね。
水分補給をスムーズにするコツ【シーン別】

「いつ・どこで・どうやって飲ませるか」をシーンごとに決めておくと、毎日の水分が安定します。難しいテクニックは不要です。愛犬の「水を飲みやすい瞬間」を増やすだけで、少しずつ前向きな変化が出てきます。
散歩や外出時の給水対策(携帯ボトル・スティックゼリー)
外では刺激が多くて落ち着きにくいので、休憩や信号待ちのタイミングで数口ずつお水をあげましょう。
ボトル一体型カップや折りたたみボウルを常備すると便利です。
「水分補給はこまめに少しずつ」という基本が習慣化していくことが理想です。
老犬や療養中でも飲みやすい工夫
お水の器の高さを首肩の負担が少ない位置に合わせ、浅めの器を複数設置することで、老犬の「行きやすい場所」を増やしましょう。
香りが立つぬるめのスープやゼリーを食事に添えると、噛む力や嗅覚が落ちてきたコでも口にしやすくなります。
小分け・回数多めでゆっくり飲ませ、体調に合わせて量を微調整してください。
夏場の熱中症予防に効果的な与え方
外出の30分前から少しずつ飲ませ、散歩は涼しい時間帯に短め・休憩多めで行います。
帰宅後はゼリーやスープでおかわりを用意し、上がった息が落ち着くまで無理なく補給をしましょう。
車内やアスファルトの照り返しは体温が一気に上がるため、こまめな日陰休憩と水分で先手を打つのがポイントです。
寒い季節(秋冬)の水分補給で気をつけたいこと
寒い日は喉の渇きを感じにくいので、常温〜ぬるめの温度にして香りを立たせると飲み始めやすくなります。
金属臭が気になるコは陶器や樹脂製の器に替え、家の数か所に浅めの器を置くことで、水飲み場まで「見つけやすく・行きやすく」しましょう。
散歩後は温かめのスープやゼリーでほっと一息、を習慣にすると、喜んで飲んでくれるコも多いようです。
ポイント
水分補給をスムーズにするコツは「習慣化」です。
手作りでできる犬の水分補給レシピ

「飲まない日が続く」「おやつ感覚で水分をとらせたい」
そんなときは、家にある材料で作れるやさしい味のスープや犬用ゼリーが役立ちます。ここでは、飼い主さんでも無理なく続けられる作り方と、安全のための注意点をまとめます。
やさしい味のスープレシピ(だし+野菜)
基本は「薄味・素材の香りだけ」にしてください。
にぼし・かつお・昆布のだし、鶏むねのゆで汁などを塩分・香辛料なしでごく薄めにし、にんじん・キャベツ・かぼちゃ等を柔らかく煮てペースト状にします。
常温〜ぬるめにすると香りが立って飲み始めやすく、食事に小さじ数杯を添えるだけでも総水分量の底上げになります。
タマネギ・ネギ類・ぶどう・キシリトールなど犬に有害な食材は入れないでください。
寒天・ゼラチンで作る犬用ゼリー
寒天とゼリーは、どちらも無糖のだしやゆで汁を薄め、甘味料・塩分は加えずに作るのが基本です。
初日は少量から様子を見て、うんちと食欲が普段通りかを確認しましょう。
寒天は常温で固まりやすく角切りにしやすい一方、食物繊維が多いので与え過ぎると便が緩むことがあります。
ゼラチンは口どけがよく、ぷるんっと食べやすい反面、動物由来のたんぱく質なのでアレルギー歴のある子は少量から始めてください。
手作りと市販ゼリーの違い・注意点
手作りゼリーは香りや濃さを愛犬仕様に調整できるのが魅力です。一方、衛生管理・保存性に注意が必要です。
市販の犬用ゼリーは、原材料や硬さが一定で扱いやすく、忙しい日でもコンスタントに水分を確保しやすいのが利点です。
普段は市販で安定、時間のある日は手作りで香りアップ、という目的に応じて使い分けても問題ありません。どちらも与える量は体格・運動量に合わせて調整してください。
ジュレッタで手軽に水分補給
「食べるお水」を簡単に用意したい日にはジュレッタが便利です。
水に溶かして冷やし固めるだけで、香り・食感のバランスが取れたゼリーが安定して作れます。固めずにスープのまま飲ませてあげることもできます。
粉末が小分けに包装されているため、衛生面も問題なく、保存もラクにできます。
▼愛犬の水分補給に!「犬猫用ゼリージュレッタ 下部尿路ケア」をチェック!
水分補給時の注意点と選び方のポイント

毎日の飲みやすい工夫は、小さな積み重ねがいちばん効きます。ここでは、家で今日からできる安全のコツと、迷いがちな選び方の目安をまとめました。
水の種類(浄水・白湯・ミネラルウォーター)
基本は日本の水道水で十分です。浄水器を通した水道水でも問題ありません。
冷たすぎると飲み始めにくいコの場合は、常温〜ぬるめの白湯にすると、口にしやすいことがあります。
ペットボトル水を使う場合は軟水(ミネラル控えめ)が無難です。
どの水でも毎日交換し、器はこまめに洗いましょう。
持病がある子は、主治医の指示に合わせて水の硬度や与え方を調整してください。
飲みすぎや水中毒を防ぐコツ
「こまめに少しずつ」水分補給させてあげることが安全です。
水中毒(短時間での過剰な飲水による低ナトリウム血症)は、犬ではまれな事例ですから、過度に心配しすぎる必要はありません。
プールやホース遊びでは無意識に大量の水を飲み込みやすいため、遊ぶ時間と休憩を区切ることや、遊ばせた後は落ち着いてから少しずつ補給させてあげることを心がけましょう。
添加物や香料に注意!無添加・国産を選ぼう
風味づけやゼリー・スープを選ぶ際は、犬用として設計され原材料がシンプルなものを基準にしましょう。
そういった意味では「無添加・国産」がおすすめです。
人工甘味料や過度な塩分・香料は避け、表示量を守って少量からスタートすると安心です。
国産・無添加表記でも製品ごとに中身は異なるため、原材料表示と給与量を必ず確認し、体格・季節・体調に合わせて濃さと量を微調整してください。
ポイント
「水分補給はこまめに少しずつ」
これは犬に限らず人間にもよく言われることですよね。
日本で愛犬と暮らすうえでは、水の質にこだわるよりは、頻度や量、飲みやすい環境づくりに注目することが大切です。
短時間での大量飲水、吐き気・ふらつき・ぐったりなど異変があれば早めに受診を検討してください。
犬の水分補給に関するよくある質問

飼い主さんからよく寄せられる疑問を簡潔にまとめました。
体調や季節、年齢によって最適解は少しずつ変わりますので、まずは基本の考え方から確認していきましょう。
水を飲まないとどれくらいで危険?
極端に少ない状態が半日〜1日ほど続き、尿が濃い・量が少ない・元気や食欲の低下が見られる場合は注意が必要です。
嘔吐や下痢を伴うと脱水は早く進むため、改善しない・悪化する場合は早めの受診をご検討ください。
経口補水液やポカリは与えてOK?
人用スポーツ飲料は糖分やナトリウムが犬には過剰になりやすいため常用は推奨しません。
日常は水・犬用のスープ・ゼリーで十分です。
体調不良時などで電解質が気になる場合は、犬用の経口補水を選び、表示や獣医師の指示に従って量と濃さを調整しましょう。
食欲がないときの水分補給方法は?
香りが立つぬるめのヤギミルクや野菜の出汁、食べやすいゼリーできっかけを作ると食いつきやすくなります。
器の高さや置き場所を見直し、少量を回数多めに試すのがコツです。
ぐったり・嘔吐下痢・急な体重減少などがあれば、自己判断せず受診をご検討ください。
留守番中の給水はどうすればいい?
複数の場所に浅めで安定した器を置き、清潔な水をたっぷり用意します。
こぼしやすいコには重めの器や給水ボトルの併用が安心です。 帰宅後はスープやゼリーを少量添えて、合計の摂取量をやさしく底上げしましょう。
老犬で夜間のトイレが心配。水は減らすべき?
水分制限は原則控えます。脱水や便秘の原因になることが多いためです。
就寝前1~2時間は与え方を少し控えめにする、器を寝床の近くに置く、夜間トイレの導線を整える等で負担を減らしましょう。
夜間の多飲・多尿や失禁が目立つときは、病気が隠れていないか受診で確認を。
まとめ:犬の水分補給は「おいしく・無理なく」がいちばんおすすめ

毎日の水分補給は「がんばって飲ませる」より、「愛犬が自分から飲みたくなる」工夫を重ねることが続けやすい近道です。
まずは
- ゼリーやスープで水分を摂る習慣を作ってあげる
- 外出は携帯ボトルでこまめに水分をあげる
- 日常はウェットやトッピングで水分摂取量を底上げ
- 必要に応じてサプリで微調整する
季節や年齢によって犬にとっての「水が飲みやすい形」は変わります。
暑い日は前後で少量ずつ、寒い日は常温〜ぬるめで香りを立たせるなど、シーンに合わせて調整しましょう。
器は清潔に保ち、家の複数箇所に浅めの器を置くといった環境改善で自然に水分摂取量が伸びます。
うんち・おしっこの様子、元気や食欲がいつも通りなら概ね順調のサインです。
反対に、極端な増減・ぐったり・嘔吐下痢・発熱などがあれば、自己判断せず早めにかかりつけ医へ行きましょう。
愛犬に合った方法を見つけ、おいしく・無理なく・毎日続けることが健康維持の第一歩です。
著者情報 | 獣医師監修
▼愛犬の健康維持を水分補給から!犬猫用ゼリージュレッタ 下部尿路ケア」です。
いつものフードに添えて与えるだけで、必要な水分量を摂取できます。「チキン」「かつお」「ヤギミルク」「タイ」など、豊富なフレーバーが用意してあるので、愛犬の好みに合わせて水分補給できます。香料、保存料、人工着色料は一切使用していない無添加の安全なおやつです。