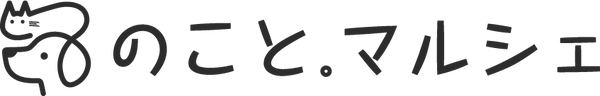「犬が水を飲まない」「急に飲む量が減ってきた気がする」と心配になっている飼い主さんに、考えられる原因と対処法を獣医師が解説します。
この記事では、犬はどのくらい水を飲まないと危険なのかの目安や、自宅でできる水分補給の工夫、受診のタイミングを整理しました。
まずは30秒で確認!愛犬の「危険度チェック」
犬が水を飲まないと感じたときは、まず
- 元気があるか
- 尿はいつも通りか
- 呼吸はいつも通りか
の3つを確認してみましょう。
例えば
- ぐったりしている
- 半日以上おしっこが出ていない
- 呼吸が荒く体が熱い
などの様子があれば、脱水や病気が進んでいる可能性があるため、すぐに動物病院への連絡をおすすめします。
一方で、遊ぶ元気があり、食欲や排尿も大きく変わっていない場合は、水分補給の工夫を試しながら、こまめに様子を見てください。
もう少し詳しく脱水の目安を知りたい方へ
毛細血管再充満時間(CRT)
:歯ぐきを指で軽く押して白くなったあと、色が戻るまでの時間の目安です。健康な犬ではおおよそ2秒以内で戻ることが多く、戻りが遅い場合は脱水や循環不全が疑われることがあります。
スキンターフ
:首の後ろや背中の皮膚を軽くつまんで持ち上げ、手を離したあとの戻り方を見る方法です。ふだんより皮膚が戻りにくい場合は脱水のサインとなることがありますが、高齢犬ややせている犬ではもともと戻りが遅いこともあるため、あくまで目安として考えましょう。
犬が水を飲まない主な原因とは?

「水を飲まない=すぐに重い病気」とは限りません。
まずは生理的な理由や環境の変化から整理して考えると、状況が整理しやすいです。
フードの種類、季節や室温、生活の変化によっても飲水量は変わりますし、ストレスや好みが影響することもあります。一方で、病気が原因で水を飲みにくくなっている場合もあります。
生理的・行動的な原因
まず多いのは、体調が悪いわけではなく、「生活や環境の影響」で飲水量が変化しているケースです。
犬がなかなか水を飲まない、生理的・行動的な原因として、例えば
- 食事から十分な水分をとれているため
- 気温が下がる冬場などは喉の渇きを感じにくいため
- 環境変化によるストレスで、落ち着いて水を飲みに行けなくなっているため
- 水の器の材質・形・高さ、置き場所が好みに合わないため
というようなものが考えられます。
病気が関係しているケース
水を飲まない原因として、体調不良や病気が隠れていることもあります。代表的には、次のようなケースが考えられます。
-
口やのどの痛み
歯周病・口内炎・口腔内腫瘍などで、しみたり痛んだりして水を飲み込みにくくなっている場合です。
-
体の痛みや動きづらさ
椎間板ヘルニアや関節炎、首や腰の痛みなどで、水を飲む姿勢をとることがつらく、結果として飲水量が減ることがあります。
-
消化器のトラブル
胃腸炎や膵炎などで吐き気や腹痛があると、食欲と一緒に水を飲みたい気持ちも落ちてしまうことがあります。
-
内臓疾患や全身状態の悪化
腎臓病・肝臓病・糖尿病などの慢性疾患や、発熱をともなう感染症などでぐったりしていると、水を飲む元気が出ないことがあります。
「元気がない」「食欲が落ちている」「尿の色や回数がいつもと違う」など、水以外の変化も同時にみられるときは、生理的な原因と決めつけず、早めに動物病院で検査を受けることが大切です。
今すぐできる!水を飲ませる10の工夫【禁忌つき】

危険なサインがない場合は、自宅での工夫だけで飲水量が少しずつ改善することもあります。
ここでは、今すぐ試しやすい工夫と、実はおすすめできない対応を紹介します。
どの方法も「無理に大量に飲ませる」のではなく、愛犬が自分から飲みたくなる環境づくりを意識してくださいね。
風味づけで飲みたくなる工夫を
味のない水だけでは飲まない子でも、少し香りを足すと興味を示すことがあります。 塩分を加えていない茹でささみのゆで汁や犬用スープを、ごく少量だけ水に混ぜて試してみましょう。
味を濃くしすぎず、少量から始めて、おなかの調子を見ながら続けることが大切です。
▼水を嫌がる子の“きっかけ作り”として!犬猫用ゼリージュレッタ 下部尿路ケア」がおすすめです。
いつものフードに添えて与えるだけで、必要な水分量を摂取できます。愛犬の水分補給の補助としてぜひお試しください。
水温や器を変えて“お気に入り”を見つけよう
冷たい水が好きな子もいれば、常温やぬるま湯を好む子もおり、水温だけで反応が変わることがあります。
ステンレス・陶器・ガラスなど器の材質や器の高さも飲みやすさに影響しますので、負担の少ない姿勢で飲める器を探してみることもおすすめです。
清潔な水をこまめに交換してリセット
水が古くなっていたり、器にぬめりが残っていたりすると、犬が近寄りたがらないことがあります。
少なくとも1日1〜2回は器を洗って水を入れ替え、暑い季節はさらにこまめな交換を心がけましょう。
家の中の複数の場所に水飲み場を用意しておくと、「ついで飲み」が増えて、1日の飲水量アップにつながりやすくなります。
フードで水分をとらせる工夫
水皿からほとんど飲まない場合は、食事から水分をとってもらう方法もあります。
ドライフードをぬるま湯でふやかしたり、獣医師と相談のうえでウェットフードの比率を少し増やしたりすると、自然に水分量を増やせます。
腎臓病や心臓病など持病がある場合は、フードの変更が負担になることもあるため、自己判断では大きく変えないようにしましょう。
どの年齢でも安心してあげられる、【国産・無添加】犬猫用ジビエで作ったスープの素(鹿/猪)もおすすめです。
ストレスを減らす環境づくり
緊張やストレスが強いと、水を飲みに行きにくくなる犬もいます。
テレビの前や人の行き来が多い場所は避け、静かで落ち着ける位置に水を置くようにしましょう。
多頭飼育の場合は、ほかの犬から離れた場所に水飲み場を作ると、ゆっくり飲めるようになることがあります。
叱りながら促すのではなく、さりげなく勧めることがポイントです。
やってはいけないNG対応
水分補給のつもりでも、次のような方法は避けた方が安全です。
- シリンジやスポイトで、水を一気に流し込む
水が気管に入ってむせてしまい、肺炎を起こす危険があります。特にシニア犬や持病のある子には避けましょう。
- 人間用のスポーツドリンク・味噌汁・濃いスープなどをそのまま与える
塩分や糖分が多く、腎臓や心臓に負担になることがあります。
- 牛乳を「水の代わり」にたくさん飲ませる
体質によっては下痢やおなかの不調の原因になります。
- これらの方法だけに頼って受診を先延ばしにする
脱水や病気の悪化を見逃すおそれがあるため、「おかしいな」と感じたら早めに動物病院へ相談してください。
犬が水を飲まないとどうなる?危険度と時間・日数の目安
| 状況 | 目安 | 対応 |
|---|---|---|
| 元気だが飲まない | 半日未満 | 自宅で工夫しながら観察 |
| 元気が低下・尿が少ない | 半日 | 病院へ相談 |
| ぐったり・嘔吐/下痢・発熱 | 時間に関わらず | 受診 |
何時間飲まなかったら危険なのかを一律に決めることはできませんが、健康な成犬の目安としては、丸1日近くほとんど水を飲まない状態が続くのは望ましくありません。
持病のある子では、そこまで待たず、半日程度の変化でも相談したほうが安心です。
嘔吐や下痢を伴っている、ぐったりしている、半日近くおしっこが出ていない、といったサインがあれば、経過時間にかかわらず受診を優先してください。
老犬・術後・季節など状況別の注意ポイント

子犬・老犬・持病がある犬・暑い季節では、数時間でも脱水が急に進むことがあります。それぞれの場面ごとに、少し慎重に様子を見てあげることが大切です。
老犬・寝たきりの子の場合
老犬や寝たきりの犬は、喉の渇きを自覚しにくく、水飲み場まで行くこと自体が負担になりがちです。
器をベッドの近くに置く、少し高めの台に乗せるなど、飲みに行きやすい・楽な姿勢で飲める工夫をしてあげましょう。
尿の回数や色、呼吸の変化が気になるときは、早めにかかりつけの動物病院に相談してください。
抜歯・麻酔・薬の後に飲まないとき
全身麻酔や抜歯の後は、麻酔の影響や口の痛みで、すぐには水を飲みたがらないことがあります。
動物病院から指示されたタイミングや量の目安を守り、少量ずつ与えましょう。
指示された時間を過ぎてもまったく飲まない、何度も吐く、ぐったりするなどの様子があれば、自己判断で様子を見続けず、手術を受けた病院へ連絡してください。
夏バテや冬の寒さによる変化
夏は呼吸が増えることで水分が失われやすく、熱中症や急な脱水につながるおそれがあります。
一方、冬は喉の渇きを感じにくく、暖房による乾燥で少しずつ水分不足になることがあります。
季節に合わせて室温と湿度を整え、夏はこまめな給水、冬は飲むきっかけを意識して増やしてあげると安心です。
散歩中や外出先で飲まない理由
散歩中や外出先では、周囲がにぎやかで落ち着かず、いつもと違う器やにおいのする水を警戒して飲まない犬も少なくありません。
こまめに日陰で休憩をとり、家と同じ器や飲み慣れた水を携帯すると飲んでくれることがあります。
飲水量の “かんたん記録” のコツ
細かい量を正確に量ろうとしなくても、いつもと比べてどうかが分かれば診察の役に立ちます。例えば、次のような方法がおすすめです。
- 毎回同じカップやボウルで水を入れ「だいたいこのくらい入れている」と自分の基準を決めておく
- 朝・夜など区切りのタイミングで、水の残量が分かるようにスマホで器を撮影しておく
- 「○時ごろによく飲んだ」「散歩のあとに少しだけ飲んだ」などを、メモアプリに一行ずつ簡単に記録する
ざっくりとした記録でも、数日分まとまっていると、受診時に獣医師が変化の傾向を把握しやすくなります。
受診の目安と動物病院に持参したいチェックリスト

基本的には、水を飲まないことに加えて、他の気になる症状が出ているときは、早めの受診をおすすめします。
例えば
- ぐったりしている
- 半日以上おしっこが出ていない
- 呼吸が荒く体が熱い
といった場合は、様子を見るよりも動物病院を受診しましょう。
犬が水を飲まないとどうなる?危険度と時間・日数の目安でもお伝えした通り、健康な犬でも丸1日水を飲んでいない状態であれば、受診をおすすめします。
受診時には
- いつから水をあまり飲まなくなったか(きっかけや前日との違い)
- その間の尿の回数・量・色
- 食欲や元気の変化(普段の何割くらい食べているか・遊ぶかどうか)
- 水以外に気になる症状の有無
という情報を獣医師に伝えると、診察がスムーズです。
再発を防ぐための毎日のルーティン

毎日のちょっとした工夫で、脱水や体調悪化のリスクを減らし、早めに変化に気づけるようにしておくことが大切です。完璧を目指す必要はありませんので、できそうなところから少しずつ取り入れてみてください。
-
ふだんの飲水量とトイレのパターンを把握する
「その子の普通」をざっくり意識しておき、急な変化に気づけるようにします。 -
清潔な水をいつでも飲めるようにしておく
1日1〜2回は器を洗って水を交換し、家の中の複数の場所に水飲み場を用意しておくと、自然と飲む回数が増えやすくなります。 -
フードと組み合わせて水分をとる習慣をつくる
ドライフードをぬるま湯でふやかす、ウェットフードや水分補給ゼリー・スープなどを上手に取り入れ、食事からの水分も意識しましょう。 -
季節や年齢に合わせて環境を整える
夏は暑さ対策とこまめな給水、冬は乾燥に注意しながら、老犬や持病のある子には器の高さや置き場所も含めて飲みやすい環境を維持します。
ポイント
人それぞれに「普通・正常」が違うように、犬によってどの程度が「正常」と言えるか微妙に異なります。
愛犬がいつもはどうなのか、一番よくわかっているのは飼い主さんです。
いつもの様子から大きくズレたときは受診を検討する、という考えが軸にあると、迷いにくいかもしれません。
まとめ
犬が水を飲まないからといって、必ずしも重い病気とは限りませんが、元気・食欲・尿のようすにいつもと違う点がないかを一緒に確認することが大切です。
危険なサインがなければ、風味づけや器・水温の工夫、フードと組み合わせた水分補給などで「自分から飲みたくなる環境づくり」を意識してみてください。
一方で、ぐったりしている、半日以上おしっこが出ていない、丸1日近くほとんど水を飲んでいないといった様子があれば、自己判断で様子を見続けず、早めにかかりつけの動物病院に相談しましょう。
FAQ(よくある質問)
多くの飼い主さんが気にされるポイントを、Q&A形式でまとめました。
愛犬の年齢や持病、季節などによって判断が変わることがありますが、あくまで一般的な目安を回答しています。
Q1. 犬が水を飲まないとどうなる?何時間で危険?
健康な成犬でも、丸1日ほとんど水を飲まない状態が続くと、脱水が進み、
- 尿が減る・濃くなる
- ぐったりする
- 食欲が落ちる
といった変化が出るおそれがあります。
子犬や老犬、持病のある犬では、半日でも危険度が上がります。
このような変化が見られたら、当日中の受診を検討した方が安心です。
Q2. 元気だけど水を飲まないときは?
元気と食欲があり、おしっこの回数や色も普段どおりであれば、フードの水分量や季節、環境の影響で一時的に飲水量が減っている可能性もあります。
まずは風味づけや器・水温の工夫、フードで水分を補う方法などを試してみてもよいでしょう。
Q3. 牛乳や人用スープを水の代わりにしても大丈夫?(結論:基本NG)
人間用の牛乳や味噌汁、スープ、スポーツドリンクなどは、塩分や脂肪・糖分が多く、下痢や内臓への負担につながることがあるため、水の代わりとしてたくさん与えることはおすすめできません。
与える場合は、犬用に作られたミルクやスープ製品を選び、表示量を守りながら「あくまで水分補給の補助」として使いましょう。
著者情報 | 獣医師監修