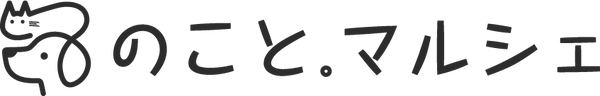「うちの愛犬、最近うんちが出にくそう…」「便秘に効く食べ物ってあるの?」
そんな悩みを持つ飼い主さんに向けて、犬の便秘を食事や日常ケアでサポートする方法を、詳しく解説します。
犬も便秘になる?よくある症状と原因

犬の便秘は、決して珍しいトラブルではありません。
特に高齢の犬や水分摂取量が少ない犬では起こりやすく、飼い主が見逃してしまうと症状が悪化することもあります。
便秘は一過性のものもあれば、病気の兆候であることもあるため、正しい知識と早めの対応が大切です。まずは、犬の便秘にどのような特徴や原因があるのかを整理しておきましょう。
犬の便秘チェック|何日出ないと便秘?
一般的に、犬が2日以上排便していない場合は便秘の兆候と考えられます。
3日以上出ない場合や、食欲がなく元気もない場合は、病気の可能性もあるため、早めに動物病院を受診してください。
ただし、1日排便がなくても明らかに腹部が張っていたり、排便の姿勢をとっても出ない様子がある場合は要注意です。
以下のような症状が見られたら、便秘を疑いましょう。
- 排便姿勢をとるがうんちが出ない
- 出ても少量で、硬くコロコロしている
- いきんで苦しそうにしている
- お腹が張っている、触ると嫌がる
なお、食欲がある・元気がある場合と、元気がない・嘔吐がある場合では緊急性が異なります。後者はすぐに動物病院を受診してください。
水分不足・食事内容・運動不足が主な原因
犬の便秘の主な原因は以下の3つです。
- 1.水分不足
- ドライフード中心の食事では水分摂取量が少なくなり、便が硬くなりやすくなります。
- 2.食事の内容
- 食物繊維が少なかったり、脂肪が多すぎたりすると、腸の動きが悪くなることがあります。また、人間の食べ物を与えることで腸内バランスが乱れるケースも。
- 3.運動不足
- 室内犬やシニア犬に多いですが、運動不足は腸の”ぜん動運動”を鈍らせ、便秘につながります。
こうした生活習慣の積み重ねによって、慢性的な便秘になる犬も少なくありません。
腸のぜん動運動とは

腸の壁にある筋肉がリズミカルに収縮と弛緩を繰り返すことで、腸の内容物を肛門側へと押し出し、移動させる運動を指します。
消化が終わった残渣や老廃物を便として体外に排出するために、腸の内容物を肛門方向へ運ぶだけでなく、食べ物や消化液を混ぜ合わせながら消化・吸収を助ける役割があります。
老犬・子犬は便秘になりやすい理由
年齢によっても便秘のリスクは変わり、それぞれのライフステージに合った対策が求められます。
- ・老犬・シニア犬
- 腸の動きが鈍くなるほか、筋力の低下や水分摂取量の減少、持病の薬の副作用なども便秘の原因となります。
- ・子犬
- まだ腸の働きが未熟なため、環境の変化やストレス、食事内容によって便秘になりやすい傾向があります。
便秘が病気のサインである場合も
便秘は単なる食事や生活の問題だけでなく、病気の症状の一部であることもあります。
- 前立腺肥大(特に去勢していないオス犬)
- 骨盤や脊椎の変形(老犬に多い)
- 消化器の腫瘍やポリープ
- 肛門周囲の異常(肛門腺炎や狭窄)
このような疾患により、物理的に便が通過しづらくなることがあります。
犬の便秘にいい食べ物!おすすめの食べ物と食事法

犬の便秘対策には、「何を食べさせるか」は非常に重要です。腸内環境の改善、便のかさ増し、水分の補給といった観点から、便秘に効果的な食材や与え方があります。
ここでは、安全かつ効果的に取り入れられる食事法をご紹介します。
ヨーグルトは便秘に効果的?与える量と注意点
ヨーグルトは一部の犬では便通が改善することもありますが、多くの犬は乳糖不耐症であるため、下痢や腹部不快感のリスクがあります。
また、人間用ヨーグルトの乳酸菌は犬の腸に定着しづらく、腸内環境改善効果は限定的です。したがって、人間用ヨーグルトを犬に与えることは基本的に推奨されません。
しかし、一時的に便通がよくなる事例もあるため、獣医療の実務では“完全禁止”とまではされていません。試したい場合は、ごく少量から慎重に行いましょう。
与え方のポイント:
- プレーンヨーグルト(加糖・人工甘味料なし)を選ぶ
- 小型犬でティースプーン1杯程度/日から始める
- 下痢や嘔吐など消化器症状が出た場合は中止する
- 主食を置き換えるものではなく、トッピングやおやつの範囲で活用
一時的に便通がよくなることはありますが、長期的な整腸効果や便秘改善が保証されているわけではないということを押さえておきましょう。
犬の乳糖不耐症とは?
犬の乳糖不耐症とは、牛乳や乳製品に含まれる「乳糖(ラクトース)」という糖をうまく分解・吸収できない体質のことを指します。
子犬期には乳糖を分解する酵素「ラクターゼ」が活発ですが、離乳後は多くの犬でその活性が低下するからです。
よって、犬の大多数は成犬になると乳糖不耐症であると考えてよいでしょう。
ちなみに、ヤギミルクは乳糖の含有量が牛乳と比べて少なく、消化がしやすいといわれています。
ヤギミルクにも乳糖が含まれているため、少量から与えて犬の反応を確認することが重要ですが、犬にとってはより安全な選択肢でしょう。
食物繊維が豊富なフードや食材(キャベツ・さつまいも・かぼちゃなど)
便のかさを増やし、腸の動きを助けるためには、適量の食物繊維を含んだ食材が役立ちます。犬が比較的受け入れやすく、安全性が高いのは以下のような野菜です。
- キャベツ:水溶性・不溶性繊維をバランスよく含む。細かく刻んで茹でて与える。
- さつまいも:便を柔らかくする効果があり、腸の動きを助ける。加熱し皮をむいてから与える。
- かぼちゃ:βカロテンや食物繊維が豊富で、消化にもやさしい。無塩で加熱調理が基本。
注意点としては、「食物繊維=多ければ良い」わけではありません。摂りすぎると逆に便が詰まることもあるため、トッピングとして少量から始めましょう。
▼愛犬のおなかの調子を整える「サイリウム (オオバコ)犬猫用」をチェック!
犬用・猫用のサイリウム(ナチュラルサイリウム)は、オオバコ100%の食物繊維です。
無味無臭でパウダー状になっており、いつものフードに添えてあげることで、愛犬愛猫のお腹の調子を整える効果が期待できます。
ウェットフード・スープ・犬用ミルクで水分をプラス
便秘の犬は、総じて水分摂取量が不足している傾向があります。
ドライフード中心の食生活では、体内での水分利用も限られがちです。以下のような工夫で水分摂取をサポートできます。
- ドライフードに水や犬用スープを加える
- ウェットフードを取り入れる
- 犬用ミルクを与える
特に高齢犬や暑い時期の脱水対策にもつながります。
▼いつものご飯にトッピングがおすすめ!愛犬の水分補給が簡単に!?犬猫用ゼリー「ジュレッタ」です。
いつものフードに添えて与えるだけで、必要な水分量を摂取できます。「チキン」「かつお」「ヤギミルク」「タイ」など、豊富なフレーバーが用意してあるのでおいしく水分補給できます。香料、保存料、人工着色料は一切使用していない添加物不使用の安全なおやつです。
老犬におすすめの便秘対策フードとトッピング
老犬は、腸の働きだけでなく、飲水量や筋力の低下、薬の影響など複数の要因で便秘になりやすくなります。そのため、高繊維+消化サポート+水分補給の3点を意識した食事が重要です。
- シニア用消化ケアフード
- ふやかしたドライフード+野菜ピューレ(かぼちゃ・さつまいもなど)
- 水分を補えるスープ仕立ての犬用フード
また、フードの切り替えは急に行わず、7日ほどかけて徐々に混ぜて慣らすことをおすすめします。
犬のコロコロうんちを改善したいときの食材・対策
コロコロと乾燥した便は、水分不足や繊維不足が原因です。このタイプの便には以下のアプローチが有効です。
- 水分を含む食材(かぼちゃ、さつまいもでも可)を加える
- ドライフードに温水をかけてふやかす
- オリゴ糖・乳酸菌などの腸活サプリを併用する
1日の飲水量を体重1kgあたり50〜60mlを目安に確保するのが望ましいため、それを下回る場合は意識的に水分を摂らせる環境を整えましょう。
犬の便秘に良くない食べ物とは?

犬の便秘対策では、良い食べ物を与えるだけでなく、便秘を悪化させる可能性のある食材を避けることも大切です。
脂肪分の多い食品
まず注意したいのが脂肪分の多い食品です。
揚げ物や脂の多い肉、人間の料理の残りなどは、腸の動きを鈍らせ、便が滞る原因になります。
食物繊維のとりすぎ
そして、意外とやってしまいがちなのが食物繊維のとりすぎです。繊維は腸の働きを助ける一方で、過剰だとかえって便が硬くなり、排便しにくくなることもあります。水分と一緒に、少しずつ与えるのが基本です。
人間用のお菓子や加工食品
人間用のお菓子や加工食品も避けるべきです。砂糖や添加物は腸内環境を乱し、便秘や体調不良の原因になるため、誤って与えないよう注意しましょう。
食べ物以外でできる犬の便秘対策

腸の働きは、運動や生活習慣、水分摂取などさまざまな要素に左右されるため、食事だけで解決しない場合は、日常ケアの工夫もしてみましょう。
犬の便秘に効くお腹マッサージの方法
軽度の便秘や「出そうで出ない」といった状態には、お腹のマッサージが有効なことがあります。マッサージにより腹部を刺激し、腸の動きを助けることが目的です。
マッサージの手順:
- 犬をリラックスさせ、横向きまたは仰向けに寝かせます。
- おへそ周辺、特にやや下腹部(臍下)を中心に、時計回りに優しく撫でるように円を描く動きを行います。
- 1回につき3〜5分程度、1日1〜2回を目安にします。
※嫌がる場合や、腹部を触られると痛がる場合は、無理に続けず、獣医の診察を受けてください。
この方法は、排便のきっかけがつかみにくいときや、腸の動きを穏やかに促したいときに有効です。マッサージは、便を直接排出させるものではなく、腸のぜん動運動を助け、正常な便通をサポートする補助的なケアとして活用できます。
スキンシップにもなるため、日常のケアに取り入れると良いでしょう。
散歩や運動の工夫で腸を刺激する
運動不足は犬の便秘の大きな原因のひとつです。腸のぜん動運動は、身体全体の動きと連動しているため、散歩や軽い運動を取り入れることで腸が自然に刺激されます。
便秘対策としての運動のポイント:
- 毎日20分以上の継続的な散歩を心がける(可能なら朝と夕方の2回)
- 歩く速度を少し速めにする/軽い坂道や土の地面を選ぶと、より腹部が刺激されやすい
- 室内でのボール遊びや引っ張り合いも、軽い運動として効果的
特に高齢犬や関節疾患のある犬には無理は禁物ですが、無理のない範囲での運動量アップは便通改善に大きく寄与します。
水を飲まない犬への水分補給のコツ(ゼリーなど)
水分不足は便秘の直接的な原因となりますが、「水をなかなか飲まない」という悩みを持つ飼い主も少なくありません。自然に水分を摂らせる工夫が、便の柔らかさや排便のスムーズさを左右します。
飲水量を増やす工夫:
- 水を少し温める(ぬるま湯にする)ことで、香りが立って飲む犬も多い
- 犬用ミルクや無添加のだし汁を水に混ぜる
- ウェットフードやふやかしたフードを活用し、食事から水分を摂取させる
- 犬用ゼリー(無糖・無添加)をおやつやトッピングに使用
飲水量の目安は、体重1kgあたり50〜60ml/日程度。明らかに足りていない場合には、食事全体を見直し、「飲ませる」よりも「食事に含める」工夫を優先するのが現実的です。
犬の便秘におすすめのサプリ・オイル・漢方

補助的に使えるサプリメントやオイル、動物病院での治療も選択肢となります。軽度の便秘であれば、こうした対策で排便リズムが整うこともあります。
食物繊維を補うサプリメント(例:サイリウムなど)
食物繊維は便のかさと柔らかさを保つために重要な成分です。フードで十分に摂れない場合や、食材の調整が難しいときには、繊維補助サプリメントの活用が有効です。
サイリウムとは、オオバコ科の植物から得られる天然の食物繊維です。水溶性繊維が豊富で、便に水分を含ませつつ、かさを増して自然な排便を促進します。
サプリ使用時の注意点:
- 十分な水分摂取と併用しなければ逆に便が硬くなるリスクがあります。
- 体重に応じた使用量を守り、最初はごく少量から始めることが原則です。
乳酸菌やオイル
- 乳酸菌サプリ
- 善玉菌を増やすことを目的とした「腸活サプリ」つまり乳酸菌サプリは、便通改善の報告例は多数あり、臨床的にも一定の効果が認められています。
- 便秘対策としてのオイル
- ごく軽度の便秘であれば、食事にオイルを少量加えることで便の滑りを良くし、排便を助けることがあります。
オイルはあくまで一時的な補助的手段であり、長期的な便秘管理には向きません。
これらは、動物病院で処方される医薬品の治療をベースに、補助として使うケースがあります。治療中の際は必ず獣医師に確認の上使用してください。
動物病院で処方される薬の例

診察のうえで体質や状態に合った薬が処方されます。
獣医療で使われる主な薬剤例:
・ラクツロース:腸内での浸透圧を利用して便を柔らかくする。猫にもよく使われる。
・乳酸マグネシウム:水分を腸内に引き込む効果があり、便の排出を助ける。
・浣腸薬(動物専用):即効性はあるが、繰り返し使用は粘膜障害や自力排便低下のリスクあり。
必ず獣医師の指導のもと使用してください。
犬の便秘Q&A|気になる疑問を解決!

犬の便秘は、ただ「出ない」だけでなく、飼い主さんにとっても判断が難しい症状のひとつです。
「病院に連れて行くべき?」「繰り返す下痢と便秘はどうすれば?」といった、よくある疑問にQ&A形式でお答えします。
犬の便秘、病院に連れていくタイミングは?
「2日排便がない」「苦しそうにいきむけれど出ない」など、軽度な便秘であればまずは自宅で食事や水分を見直すことが一般的ですが、以下のような症状があればすぐに病院を受診してください。
受診を勧めるタイミング:
- 3日以上排便がない
- 何度もいきんで苦しそうにしているが便が出ない
- 嘔吐・食欲不振・元気がないなどの全身症状を伴う
- 腹部が張っていて痛がる・触ると嫌がる
- 排便時に出血がある
これらの症状は、単なる便秘ではなく、消化管閉塞・前立腺肥大・腫瘍・異物誤飲などの重大な疾患が隠れている可能性もあるため、自己判断せず獣医師の診察を受けるべきです。
便秘と下痢を繰り返す場合の対処法は?
「便秘が治ったと思ったら今度は下痢」「また詰まり気味で、便通が安定しない」――このように便秘と下痢を繰り返す犬は、腸内環境の乱れや慢性腸炎、食事の不適合が背景にある可能性があります。
原因として考えられるものの例:
- 腸内細菌バランスの乱れ(悪玉菌優位)
- 繊維不足や水分不足、過剰なタンパク質や脂肪
- 過敏性腸症候群(IBS)や炎症性腸疾患(IBD)
- フードローテーションが合っていない、頻繁な変更
対処のポイント:
- 食事内容を見直し、低アレルゲン・消化に配慮したフードへ切り替え
- 整腸サプリ(乳酸菌・オリゴ糖)や食物繊維の補助
- 状況に応じて血液検査・糞便検査・超音波検査などでの評価が必要
症状が長引く場合や、下痢と便秘を長く繰り返すようなら、必ず動物病院を受診してください。
犬が便秘でお腹がパンパンなときの応急処置は?
犬の腹部が明らかに張っていて、排便ができずに苦しそうな場合、応急処置はあくまで一時的な対処であり、原則として早急に病院へ連れていくべき状態です。
応急対応の原則:
- 無理に排便させようとしない(浣腸などは危険)
- マッサージや刺激は避ける(腹部疾患のリスクあり)
- 飲水が可能であれば、少量ずつ水分を与える
- 絶食はしないが、脂っこい食事や繊維の多いものは避ける
腹部膨満には、
- 単なる便の貯留
- ガスの停滞(鼓脹)
- 腫瘍・子宮蓄膿症・腹水
など、緊急を要する疾患が隠れている可能性もあります。
「とりあえず様子を見る」は禁物であり、お腹が明らかに張っていて排便がない場合は、すぐに動物病院で診察を受けましょう。
まとめ:犬の便秘は食べ物と日々のケアで改善できる!

犬の便秘は、多くの場合、食事・水分・運動・腸内環境など、日々の生活習慣の見直しで改善が期待できます。
繊維や水分を意識した食事、腸にやさしいサプリメント、軽い運動やお腹のマッサージなど、ちょっとした工夫の積み重ねが、自然な排便リズムの回復につながります。
ただし、症状が長引いたり、元気や食欲に変化がある場合には、早めに動物病院で相談することが大切です。便秘の陰に、見逃してはいけない病気が隠れていることもあります。
毎日の観察とケアを通じて、愛犬の健康な腸と快適な生活をサポートしてあげましょう。
著者情報 | 獣医師監修