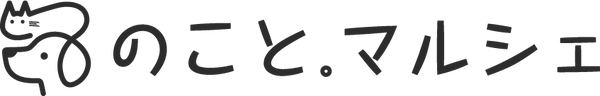犬の膀胱炎について、獣医師がポイント付きで解説します。
犬の膀胱炎は再発しやすい一方で、原因を見極め、治療と日々のケアを丁寧に続ければ改善・予防は十分に可能です。
大切なのは、「食べてはいけないもの」を避けるだけではなく、細菌感染なのか結石が関係しているのか等の背景をかかりつけ動物病院と正しく確認し、その状態に合った食事管理を行うことです。
犬の膀胱炎で食べてはいけないもの一覧

犬の膀胱炎は細菌感染だけでなく、尿結石が関与していることがあります。
したがって犬の膀胱炎で食べてはいけないものは、以下の2タイプに分けて考えるとわかりやすいです。
- 膀胱炎の犬であれば皆注意した方が良い食べ物
- 結石タイプ別に注意が必要な食べ物
高塩分や味付けされた食べ物(人間用食品)
ベーコン、ハム、スナック菓子、汁物など塩分の多い人間用食品は避けましょう。
一部の尿石用療法食では、ナトリウム量などの栄養設計により飲水・尿量を高める製品もあります。しかし、それは処方設計上の添加であり、家庭で塩分を足したり塩辛い食品を与えるのは禁物です。
加工肉・脂肪分の多い食事
加工肉は高塩分になりがちで、脂肪分の多い食事は栄養バランスを崩しやすいため不適切です。
限られた食材で作る手作りフードや人間用食品を与えることは、必須栄養素の過不足を招きやすいことが知られています。膀胱炎の治療・予防目的でも、総合栄養食または療法食を基本にするのが安全です。
おやつや間食の与えすぎ
おやつ・トッピング・手作り具材は、尿のpHやミネラル濃度に影響します。つまり膀胱炎の治療がしっかり終了するまでは、療法食の効果を弱めることがあるため、おすすめしません。 どうしても与える場合でも総摂取カロリーの10%以内を目安とし、内容はかかりつけ動物病院と共有してください。
膀胱結石を悪化させる可能性のある食材
膀胱炎が結石を伴う/疑われるときは、結石タイプ別に以下の食材・与え方を避けます。
- ストルバイト(リン酸アンモニウムマグネシウム)
- 自己判断で尿酸化剤や塩分を追加しない/通常フードやおやつを混ぜない。処方食のみでの管理が基本です。
- シュウ酸カルシウム
- ほうれん草・ビーツ・ナッツ・ルバーブなどシュウ酸の多い食材は控えます。さらにビタミンC(アスコルビン酸)高用量のサプリは体内でシュウ酸に代謝され得るため推奨されません。
- 尿酸塩(尿酸アンモニウム)
- 内臓(レバー・腎)、アンチョビ・イワシ等の青魚など高プリン食材は制限し、低プリンの処方食を中心にします。
- シスチン
- 高動物性タンパクや高ナトリウムの食事・おやつは避け、低タンパク・低ナトリウムで尿をアルカリ化する処方食を与えます。
注意点
療法食実施中に他の食べ物を混ぜないことが、治療の成否を左右する要因であることが明らかになっています。
ポイント
どの結石タイプでも「療法食+十分な水分+単独給与」が基本です。
他の食べ物を混ぜると目標pHやミネラル設計が崩れ、結石の溶解・再発予防効果が低下します。
こちらもあわせてチェック!
▼愛犬の下部尿路の健康維持に!「犬猫用ゼリージュレッタ 下部尿路ケア」をチェック!
犬の膀胱炎とは?原因と症状の基礎知識

膀胱炎は膀胱の炎症を指し、犬では多くが細菌性です。
多尿・頻尿、排尿時のいきみや痛み、血尿、尿のニオイの変化、トイレ以外での排尿などが代表的なサインですが、無症状のこともあります。
犬における細菌性膀胱炎は生涯で約14%が経験するとされ、悩まされている飼い主さんが多い疾患です。
食事での対策を考える前に、なぜ起きているかを正しく把握することが、食べてはいけないものの判断にも直結しますので一緒に確認していきましょう。
膀胱炎の仕組みと原因(細菌感染・結石など)
犬の膀胱炎の多くは、外陰部や尿道から細菌が侵入し、さらに細菌が上行して膀胱に達する経路で起こります。
原因となる細菌は大腸菌が最も多いです。
尿路の自浄作用(十分な尿流・濃縮力・粘膜バリアなど)が低下すると、細菌が定着しやすくなります。
膀胱に結石があると粘膜が傷つきやすくなりますので、細菌が付着しやすく炎症と感染が持続します。
ポイント
結石や生活環境での問題→尿路の自浄作用低下→尿道から細菌が侵入後、定着しやすくなる→膀胱炎
膀胱炎になりやすい犬の特徴
雌犬(とくに避妊雌)は雄より尿路感染症が多い傾向があります。
さらに、糖尿病や副腎皮質機能亢進症(クッシング)、腎疾患、免疫抑制状態、尿失禁や外陰部の形態異常、膀胱結石や腫瘍などの基礎疾患は再発の温床になります。
いっぽう未去勢雄での膀胱炎では、細菌性前立腺炎が潜んで尿路感染症を繰り返すことが少なくないため、評価・治療の方針が変わり得ます。
このような背景因子がある場合は、食事だけでのコントロールは困難です。結石の溶解・除去、内分泌疾患の治療、トイレ環境の見直し等、原因治療と並行した管理が必要です。
ポイント
膀胱炎になりやすい犬とは
- 雌犬(とくに避妊雌)
- 基礎疾患がある犬
糖尿病、副腎皮質機能亢進症(クッシング)、腎疾患、免疫抑制状態、尿失禁や外陰部の形態異常、膀胱結石や腫瘍
犬の膀胱炎の治し方

犬の膀胱炎に限らず、基本的には「原因を見つける→それに合った治療→家でのケア」の順で良くなります。
自己判断で薬や食事を変えると悪化することがあるため、まずは動物病院で原因を確認し、その指示に沿って進めるのが安全です。
犬の膀胱炎の検査ってどんなことをする?
膀胱炎の治療は原因の特定から始めます。
細菌感染なのか?尿路結石が原因か?そもそも基礎疾患のせいなのか?それぞれの犬の背景によって治療の進め方が変わるからです。
まずは尿検査を行うことがほとんどです。場合によっては膀胱穿刺で採取した尿で尿培養を行います。尿培養は、細菌の種類と効く薬を調べる検査といってよいでしょう。
再発例・難治例・結石疑いではX線や超音波も併用します。
ポイント
まずは尿検査!尿培養検査で使う薬を選定します。
再発やなかなか治らない場合、基礎疾患がある場合は画像検査を併用します。
全身症状がある場合は血液検査することもあります。
抗生物質や療法食による一般的な治療
細菌性膀胱炎では、尿培養検査の結果に基づいた抗菌剤を使います。
単発の細菌性膀胱炎では、短い期間(3~5日)での投与が推奨されていますが、再発を繰り返す場合や別の病気が隠れている場合は、期間や薬の選び方が変わります。
結石が関係している膀胱炎の場合、ストルバイト結石なら、適切な抗生物質と結石を溶かすための療法食で治すことが多いです。 平均1〜3か月程度かけて様子を見ます。溶解確認後も追加投与または継続が一般的です。
シュウ酸カルシウム結石は食事で溶けないため、手術や内視鏡などを検討します。
ポイント
単発の細菌感染の場合は3〜5日間の短期抗菌薬治療が一般的です。
結石や基礎疾患がある場合は、その治療が優先されることもあります。
尿結石については以下のコラムをご覧ください。
冬に知っておきたい犬猫の下部尿路疾患・尿石症
犬の尿路結石|食べてはいけないものと正しい食事法
自宅でできるケア(水分補給・トイレ環境)
再発予防には、水分を増やして尿を薄めることが大切です。
ウェットフードの活用や、ドライフードをぬるま湯でふやかす、新鮮な水をいつでも飲めるようにしておくといった工夫が役立ちます。
トイレは清潔に保ち、我慢させないことも重要です。
散歩の回数や室内トイレの機会を増やすと、膀胱の中で細菌が増えにくくなります。サプリメントは効果や相性に差があるため、使用前に獣医師へ相談してください。
▼愛犬の下部尿路の健康維持に!犬猫用ゼリージュレッタ 下部尿路ケア」です。
いつものフードに添えて与えるだけで、必要な水分量を摂取できます。「チキン」「かつお」「ヤギミルク」「タイ」など、豊富なフレーバーが用意してあるので、愛犬の好みに合わせて水分補給できます。香料、保存料、人工着色料は一切使用していない無添加の安全なおやつです。
動物病院での検査・治療が必要なケース
次のような症状があれば、受診してください。
- 排尿回数が増えるのに、出る量が少ない/何度もトイレに行く
- 排尿時に痛そう(いきむ・鳴く・陰部をしきりになめる)
- 血尿(ピンク〜赤・茶色)、にごり、強いニオイの尿
- トイレ以外での排尿、少量ずつ点々と出る、間に合わず漏れる
- 尿が出るまで時間がかかる、細く少量しか出ない
- 元気・食欲の低下や飲水量の変化などの体調変化を伴う
犬の膀胱炎は自然に治る?

犬の膀胱炎において、自然治癒を期待しての様子見は推奨できません。
多くの膀胱炎は細菌が尿道から膀胱へ上行して起こり、放置すると腎盂腎炎(腎臓に炎症を起こす病気)など重症化の可能性があります。
自然治癒は危険な理由
治療を遅らせると膀胱内で細菌が増え、炎症が長引き、細菌が腎臓に広がるリスクが高まります。痛みや頻尿・血尿が続くだけでなく、細菌が腎臓へ上行して発熱や嘔吐、ぐったりするなどの全身症状を招くおそれがあります。
放置すると症状が悪化するケース
膀胱炎の背景に結石があると、炎症が治りにくく、尿道閉塞の原因にもなります。
尿道閉塞は、雄犬にとっては構造上大変リスクが高く、結石や凝血塊が詰まると命に関わる緊急事態です。
また、腎盂腎炎まで進むと入院が必要になることもあります。
高齢犬や腎臓病・糖尿病など持病のある犬は悪化が早い傾向があります。
ストルバイト結石を食事で溶かしている最中でも、閉塞リスクはゼロではないため、動物病院の指示どおりの再診・画像チェックが欠かせません。
早めに受診すべきサイン
次のような症状があれば、できるだけ早く受診してください。
- 何度もトイレに行くのに少量しか出ない/強くいきむ
- 血尿や濃い色・強いニオイの尿、痛がる様子
- 発熱、元気・食欲低下、嘔吐、背中(腰)を触ると嫌がる
- 雄犬での排尿困難、結石の既往、1週間前後で改善しない再発例
これらは腎臓への波及や閉塞のサインになり得ます。早期の検査で原因を特定し、適切な治療に繋げることが愛犬のためになります。
犬の膀胱炎をほっとくとどうなる?

膀胱炎は自然に良くなるだろうと自己判断で様子見をすると、炎症が広がったり合併症を招いて取り返しのつかない状況になるおそれがあります。ここでは、放置した場合に起こり得る代表的なリスクを整理します。
腎臓に影響が及ぶリスク
膀胱で増えた細菌や炎症が尿管をさかのぼると、腎盂腎炎(腎臓の感染)に進行することがあります。
発熱・嘔吐・背中の痛み・ぐったりなど全身症状を伴い、入院治療が必要になる例もあります。腎臓は一度ダメージを受けると回復に時間がかかるため、早めの治療で腎臓への波及を防ぐことが重要です。
犬の腎盂腎炎とは?
膀胱など下部尿路の細菌が腎臓(腎盂)にまで上がって起きる感染症です。
膀胱炎より症状が重く、発熱・ぐったり・嘔吐・背中(腰)の痛み・濃い/ニオイの強い尿や血尿を伴うことが多いのが特徴です。放置すると急性腎障害や敗血症に進み、命に関わることがあります。治療は多くの場合入院下での点滴と抗菌薬が必要です。
尿道閉塞や結石への進行
膀胱炎をほっとくと、炎症により尿の性状が変わり、結石ができやすくなります。
とくに雄犬は尿道が細長い構造のため、小さな石や凝血塊でも詰まりやすいのが特徴です。
尿道が閉塞すると短時間で腎機能が悪化し、命に関わる緊急事態になります。
結石が背景にある場合は、石の種類に合った治療を同時に進めないと、炎症と痛みを繰り返します。
慢性化・再発の可能性
治療が不十分なまま長引くと、膀胱粘膜が荒れて厚くなる・細菌が居座りやすくなるなどの変化が起こり、慢性膀胱炎に移行しやすくなります。
さらに、基礎疾患があると再発リスクが上がるため、尿検査、必要に応じて画像検査で原因を特定し、処方どおりの治療+再発予防(十分な水分、トイレ環境、必要なら療法食の単独給与)を継続することが大切です。
ポイント
放置は腎臓への波及・尿道閉塞・慢性化につながります。つまり、命にかかわります。 迷ったら様子見せず、早めに検査と治療方針を立てることが、痛みの短縮と再発防止の最短ルートです。
犬の膀胱炎が繰り返す原因と予防法

膀胱炎は、いくつかの小さな要因が重なると再発しやすくなります。ここでは、日常で直せるところを中心に対策をわかりやすくまとめます。
生活習慣や体質
膀胱炎になりやすい犬の特徴でも紹介した通り、再発しやすい背景は短期では変えられない要素です。だからこそ、日常での補正を徹底します。
- 排尿機会を増やす:長時間の我慢を作らない。
- 清潔の維持:陰部周囲の被毛を短く保ち、湿りはドライタオル後ドライヤー弱で速やかに乾燥。
- 季節対策:冬やエアコン期は飲水が落ちやすいので、器の数を増やす/場所を分散して「ついで飲み」を誘発。
繰り返さないための食事管理
再発予防は「単独・薄める・続ける」の三原則です。
- 単独
処方(または指定)フードは単独で。おやつやトッピングは設計を崩し再発の原因になります。与えるなら総カロリーの10%以内で獣医師と内容を共有しましょう。 - 薄める
ウェットの活用/ドライをぬるま湯でふやかす/水飲み場の追加で尿を薄く保つとよいです。 - 続ける
症状が消えてもすぐ通常食に戻さない。獣医師の許可が出るまで継続することが大事です。
"薄める"に関しては濃度の問題ではなく、水分補給の意味で重要です。
三原則に加えて、犬の膀胱炎で食べてはいけないもの一覧を注意しましょう。
定期検診と尿検査の重要性
症状が落ち着いても油断は禁物です。
指示どおりの再診で尿検査をし、必要に応じて尿培養や画像検査を行います。
家庭では、排尿回数・量、色やニオイ、陰部をなめる回数、元気や食欲の変化を簡単にメモしておくと早期発見に役立ちます。
ポイント
日常の小さな積み重ね(排尿機会・清潔・飲水)+食事の三原則(単独・薄める・続ける)+定期チェックで、再発ループは断ちましょう。
飼い主さんと動物病院との連携で根気強い治療が必要です。
▼愛犬のおしっこが簡単に採れる!犬猫用おしっこチェックセットnyanpling®ニャンプリング
こんなワンちゃん・ネコちゃんにおすすめ
- 過去におしっこトラブルがあった
- 座ったままおしっこをするタイプ
- 病院での尿検査を受けたことがない
- 外出が苦手
- おしっこの量・回数・色・pHなどが気になっている
- 採尿をもっと手軽に行いたい
- 自宅で定期的に尿をチェックしたい
- 固まる猫砂を使っている
- 多頭飼い
まとめ~犬の膀胱炎は食べてはいけないものを避け、早期治療と予防を~

「うちの子は何度も繰り返してしまう…」——その不安は当然です。
大切なのは、完璧を目指すより続けられる工夫を一つずつ積み重ねること。
今日は水飲み場を一つ増やす、明日はおやつを見直す、——その小さな前進が最短の近道です。
食事療法では結果が出るまで時間を要することもあり、根気が必要です。
迷ったときは、自己判断で様子見せず、かかりつけと一緒に調整していきましょう。動物病院は、飼い主さんとその愛犬に合わせて何度でも完治に向けての治療の組みなおしをしてくれるはずです。
著者情報 | 獣医師監修