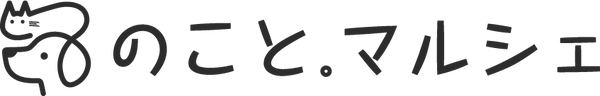「うちの子、また尿路結石かも…」そう思ったことはありませんか?
犬の尿路結石は繰り返しやすく、適切な食事管理をしなければ再発のリスクが高まります。
この記事では、犬の尿路結石について悩む飼い主さんが知っておくと良いことをまとめていますので、愛犬の健康を守りたい飼い主さまはぜひ参考にしてください。
犬の尿路結石とは?原因・症状・治療の基本

犬の尿路結石とは、尿の中のミネラル成分が結晶化して、膀胱や尿道などに「石(結石)」として沈着する病気です。
排尿にまつわる症状が現れるだけでなく、進行すると命にかかわる危険な状態に至ることもあります。
犬の尿路結石の種類
犬の尿路結石にはいくつかの種類があり、それぞれに異なる性質やできやすい条件があります。主にみられるのは以下の結石です。
- ストルバイト結石(リン酸アンモニウムマグネシウム):尿がアルカリ性に傾いたときにできやすく、細菌感染が関与することが多い。
- シュウ酸カルシウム結石:酸性尿の環境で形成されやすく、食事中のカルシウムやシュウ酸との関連がある。
- 尿酸アンモニウム結石:代謝異常や一部の犬種に特有の体質によって形成されやすい。
- シスチン結石、シリカ結石:比較的まれで、遺伝的要因や特異体質が関与する。
これらの結石は、それぞれに対策や食事療法の方向性が異なるため、獣医師による正確な診断が不可欠です。
犬の尿路結石の原因|体質だけでなく生活習慣にも関係
尿路結石の発症には、以下のような複数の因子が関係しています。
- 水分摂取量が少ないため尿が濃くなる
- 尿pHの偏り(アルカリ性・酸性どちらも要因になり得る)
- マグネシウム・リン・カルシウムなどのミネラル過剰摂取
- 細菌感染(特にストルバイト結石の形成要因)
- 遺伝的な代謝異常(尿酸アンモニウム・シスチンなど)
- トイレを我慢する習慣、運動不足による代謝低下
つまり、体質や遺伝だけでなく、食事内容や生活環境も大きく関係しています。
犬の尿路結石の症状|排尿トラブルが重要なサイン
以下のような症状がみられる場合、尿路結石の可能性があります。
- 頻繁にトイレに行くが、尿の量が少ない
- 排尿時に痛そうに鳴く、落ち着かない
- 血尿が出る(トイレシートにピンク〜赤色の痕跡)
- トイレ以外の場所で排尿するようになる
- 全く尿が出ない(この場合は緊急事態)
特に「尿がまったく出ない」状態は、尿道閉塞の可能性が高く、数時間で命にかかわる重篤なケースになることが多いです。すぐに動物病院を受診してください。
犬の尿路結石の治療法|内科治療と外科治療の選択
尿路結石の治療は、犬の状態や結石の種類・大きさ・できた部位によって異なります。
大きく分けて、「内科的治療」と「外科的治療」という2つのアプローチがあることは知っておきましょう。
内科的治療
内科的治療とは、食事療法や薬を使って、結石を体の中から溶かしたり、再発を防いだりする方法です。
ストルバイト結石のように特定の条件下で溶解できる結石には、非常に効果的な手段です。手術を行わずに治療ができるため、治療の第一選択となるケースが多いです。感染がある場合は抗菌薬も併用します。
尿路結石の種類によって、「食事療法によって結石を溶かすことができるか」「再発予防のための食事管理が有効か」が異なります。
| 結石名 | 食事療法による溶解 | 再発予防に対する食事管理 |
|---|---|---|
| ストルバイト結石 | 可能(専用療法食で溶解可能) | 有効(尿pHとミネラル管理) |
| シュウ酸カルシウム結石 | 不可(溶解できない) | 有効(Ca・シュウ酸・ナトリウム制限、水分摂取) |
| 尿酸アンモニウム結石 | 原則不可(溶解困難) | 有効(低プリン食などで再発予防) |
| シスチン結石 | 一部療法食で溶解可能(症例による) | 有効(低タンパク・アルカリ化) |
| シリカ結石 | 溶解困難 | 水分摂取の促進と高繊維食で予防的介入可 |
外科的治療
一方で、外科的治療とは、結石が大きすぎて自然排出ができない場合や、尿道を塞いで排尿困難や閉塞を起こしている場合などに行う手術です。
膀胱や尿道から直接結石を取り出すことで、症状を速やかに解消します。
尿道閉塞時には、一時的に尿道カテーテルで尿を排出させる処置も重要です。
これらの治療法を適切に選択するには、尿検査やX線・エコーなどの画像診断による正確な検査が欠かせません。
犬の尿路結石で食べてはいけない食べ物一覧

犬の尿路結石の管理において、「何を食べさせないか」は非常に重要です。
結石には種類があり、それぞれ食事との関係性が異なります。与える食べ物によっては、症状の悪化や再発の原因になることもあるため、愛犬の結石の種類を把握し、それに応じた食事制限が必要です。
ここでは、よくみられる3種類の尿路結石について、避けるべき食材や食習慣を詳しく解説します。
ストルバイト結石|リンとマグネシウムが多い食材に注意
ストルバイト結石は、尿がアルカリ性に傾いているときに形成されやすく、細菌感染が引き金になることもあります。
別名”リン酸アンモニウムマグネシウム結石”といいますが、この名の通り、避けるべき食材には、リンやマグネシウムが多く含まれる食品が挙げられます。
食べてはいけないものの例:
- 魚介類(特に煮干し、いりこ、あさり、しらす):マグネシウムが非常に多く、結石形成を促進。
- レバー、内臓肉:リンが高く、結石の原料になりやすい。
- チーズ、ヨーグルトなどの乳製品:マグネシウム、リンが多い。
- アルカリ化しやすい野菜(ほうれん草、大豆製品など):pHが上昇しやすい。
また、人用の総菜や加工品、おやつにはミネラルや塩分が過剰に含まれる場合があり、与えるのは厳禁です。
「特定のミネラル単体の摂取=結石形成」と直結するわけではありません。pHや水分摂取、感染の有無が大きな因子であることをおさえておきましょう。
シュウ酸カルシウム結石|カルシウムとシュウ酸のバランスに注意
シュウ酸カルシウム結石は、酸性尿の環境下で形成されやすく、ストルバイトとは異なり溶かすことができません。そのため、食事療法としては再発予防が治療の中心となります。
以下のような食品は、シュウ酸またはカルシウムを過剰に含むため注意が必要です。
食べてはいけないものの例:
- ほうれん草・ビーツ・さつまいも・里芋:シュウ酸が多い代表的野菜。
- 小魚や乳製品(煮干し・しらす・ヨーグルトなど):カルシウム+リンも豊富。
- チョコレートやナッツ類:シュウ酸が多く、犬にも有害。
- 手作り食でカルシウムの補い方を間違うケース:サプリメントの過剰添加などもリスク。
過剰なカルシウム摂取や、単体の野菜多給が大きなリスクになります。
しかし、カルシウムは完全に制限すべきではなく、「適量」が重要です。カルシウム不足により、腸管でシュウ酸が吸収されやすくなり、むしろリスクが増すことがありますので注意しましょう。
尿酸アンモニウム結石|プリン体に注意
尿酸アンモニウム結石は、代謝性の異常や一部犬種(ダルメシアン、イングリッシュブルドッグなど)の体質により発生します。
このタイプでは、プリン体を多く含む食品がリスク因子となります。
食べてはいけないものの例:
- レバー、白子、アンコウの肝などの内臓系食品:プリン体が非常に多い。
- 煮干し、かつお節などの乾物系:栄養が濃縮されており、プリン体含量も高い。
- ビール酵母や一部サプリメント:成分に注意。
この結石の予防には、プリン体制限+水分摂取の強化が必要となります。
共通して避けたいこと|水分不足・塩分過多・人の食べ物
結石の種類にかかわらず、以下の点はすべての尿路結石犬で共通して避けるべきです。
- 水分摂取量が少ないこと(=尿の濃縮)
- 高ミネラル・高ナトリウム食(しょっぱいおやつ・人の食事)
- pHが偏るような一部野菜の多給
- 結石のタイプを無視した食事管理
よくある誤解|ささみ・さつまいも・野菜はOK?
飼い主の方から「ささみやさつまいも、野菜なら大丈夫ですよね?」「りんごはどう?」という質問を受けることがありますが、残念ながら一概に「安全」とはいえません。
ささみ
低脂肪・高タンパクで良いイメージがありますが、シュウ酸カルシウム結石の犬ではタンパク過剰が再発リスクになります。また、ストルバイト結石の場合も療法食の効果を妨げる可能性があります。
絶対にNGというわけではありませんが、以下の行為はおすすめできません。
- ささみを日常的にトッピングしてしまう(食事の一部として固定化)
- ささみを「ご褒美」として頻繁に与える
【なぜ高タンパクに注意?】
高タンパクな食事を続けると、尿に排泄されるカルシウムが増えたり、尿が酸性に傾いたりすることがあります。
これにより、シュウ酸とカルシウムが尿の中で結びついて結晶化しやすくなり、シュウ酸カルシウム結石のリスクが高くなるのです。さらに、結石を予防するための療法食の効果を妨げることもあるため、注意が必要です。
さつまいも
一見ヘルシーですが、シュウ酸含有量が高めなため、シュウ酸カルシウム結石の犬には不向きです。
さつまいもには、可食部100gあたり約30〜60mg前後の可溶性シュウ酸が含まれます。
これはほうれん草(約600mg)ほどではないものの、犬が日常的・習慣的に与えられる量としては無視できない数値です。
蒸す・加熱することで一部は減少しますが、ゼロにはなりません。
野菜全般
野菜はすべてが危険なわけではなく、結石の種類に応じた選別が必要です。詳しくは前述した「犬の尿路結石で食べてはいけない食べ物一覧(内部リンク)」の項目をご覧ください。
療法食で治療している場合は、勝手に野菜を足さず、獣医師と相談して判断しましょう。
りんご
りんごは水分が豊富で、食物繊維やビタミンも含まれており、犬にとって比較的安全な果物の一つとされています。ただし、尿路結石の犬に与える場合には注意が必要です。
まず、りんごに含まれるミネラル(カリウムや微量のカルシウムなど)は少量であれば大きな問題にはなりませんが、「療法食を与えている犬」にとっては、他の食材を加えること自体がバランスを崩すリスクになります。
また、果糖が多いため、糖尿病や肥満傾向のある犬には適しません。種や芯の部分には有害成分(アミグダリン)が含まれるため、必ず皮をむいて果肉部分だけを少量にとどめることが重要です。
「尿路結石の犬にりんごを与えてもいいか?」と悩む飼い主は多いですが、基本は与えない方向が安全です。どうしても与えるなら、必ずかかりつけの獣医師に相談しましょう。
尿路結石の犬に適した食事管理|おすすめのおやつは?

療法食を与えている場合は、それ以外の食材やおやつを勝手に追加しないことが基本です。
愛犬がなかなか療法食を食べてくれないことが多く、これが一番難しいという飼い主さんの言い分もよくわかります。
療法食は成分バランスが極めて精密に調整されており、他の食材を加えることでバランスが崩れることがあります。そのため、獣医師もわんちゃんのために心を鬼にして飼い主さんにお願いしている次第です。
基本は療法食+水分補給|治療と予防の柱
尿路結石の種類に応じて処方される療法食は、治療と再発防止の柱です。
療法食は、ミネラルやpH、尿量などを総合的に調整するように設計されており、自己判断での食材追加や切り替えはリスクになります。
特に重要なのが水分摂取量の確保です。
水分が不足すると、尿が濃くなり結石の成分が排出されにくくなります。
水分を増やす工夫の例:
- 療法食をふやかす
- 犬用の水分補給ゼリーを併用する
- 新鮮な水を数カ所に設置
尿路結石の犬におすすめの安全なおやつとは?
療法食を与えている場合、基本的には「おやつなし」が鉄則という前提ですが、参考までに比較的安全かもしれないおやつの条件を挙げます。
- 水分が多く、リン・カルシウム・マグネシウムの含有量が低い
- 無添加・無香料・塩分不使用
- pHに大きな影響を与えない中性〜やや酸性寄りの素材
- 療法食メーカーが出している尿ケア対応おやつ
▼愛犬の下部尿路の健康維持に!「犬猫用ゼリージュレッタ 下部尿路ケア」をチェック!
再発防止に重要!日常生活でできる予防法

犬の尿路結石は一度治療しても、再発のリスクが非常に高い病気です。毎日の「食事」以外にも「トイレ」「運動」の中に、再発予防のポイントがありますので、日常生活の中で飼い主が気をつけるべきポイントを解説いたします。
トイレの我慢を防ぐ|排尿の習慣が結石リスクを左右する
長時間トイレを我慢すると、膀胱に結石のもととなる成分が滞留し、結晶化・結石化しやすくなります。
「こまめに排尿させる」ことは、尿路結石の予防においてシンプルかつ効果的な方法の一つです。
具体的な工夫の例
- 散歩は1日2回以上行い、排尿の機会をしっかり確保
- 室内でもトイレトレーニングを進め、「したい時にできる環境」を整える
- トイレシートの場所は清潔に保ち、嫌がらず排尿できる状態にしておく
特に寒い時期や留守番が多い家庭では、「我慢させていないか」意識することが大切です。
運動と体重管理で代謝を高める
体を動かすことは、血流や腎臓の働きを促進し、尿の生成や排出を助けます。
また、適正体重を維持することも、尿中ミネラルバランスを整えるために欠かせません。
- 毎日の散歩や軽い運動を継続的に行う
- 肥満傾向がある場合は食事量と運動量を見直す
- 関節疾患や高齢などで運動量が制限される場合は、室内での遊びや知育トイの活用も
運動不足は「水を飲まない・排尿が減る・体重が増える」という悪循環に直結します。
定期的な尿検査・pHチェックで早期発見
尿路結石は、無症状の段階でも尿に変化が現れていることがあります。
そのため、定期的な尿検査は再発の予防だけでなく、早期発見・早期対応にもつながります。
チェックしておきたい項目:
- 尿のpH(ストルバイトはアルカリ性傾向/シュウ酸カルシウムは酸性傾向)
- 尿比重(濃いほど結晶化しやすい)
- 血尿、細菌、結晶の有無
より正確な評価は動物病院での検査が望ましいですが、自宅でできるpHチェックや尿検査キットもあります。
愛犬のおしっこをカンタンに取れることで、尿検査のためにおしっこを動物病院に持っていくハードルも下がりますね。
よくある質問|尿路結石の犬の飼い主が悩むこと

尿路結石の治療や再発予防について調べていくうちに、「これってどうなんだろう?」と感じる疑問が次々に出てくる方も多いのではないでしょうか。
ここでは、獣医師がよく受ける質問の中から特に多い3つを取り上げ、わかりやすく解説します。
完治する?一生フード制限は必要?
尿路結石は一度治療しても再発しやすい病気であり、“完治”というより“コントロールし続ける”病気と考えるのが適切です。
特にストルバイト結石であれば、療法食で結石が完全に溶解することもありますが、その後も油断は禁物です。
- 一時的に結石が消えても、体質・食習慣が元に戻れば再発するリスクが高いです
- 多くの場合、定期的な尿検査・食事管理を継続していく必要があります
- 医師の判断で、状態が安定すれば療法食から低ミネラルの一般食に切り替えるケースもありますが、必ず獣医師の指導のもとで行いましょう
他の病気との関連性は?
尿路結石は、単独で発症することもあれば、他の病気と関係していることもあります。
- ストルバイト結石は、細菌感染(特に膀胱炎)によって発生することが多く、再発時には感染の有無をチェックする必要があります。
- 尿酸アンモニウム結石は、肝臓の代謝異常(門脈体循環シャントなど)が背景にあることも
- シュウ酸カルシウム結石は、副腎疾患や甲状腺機能異常などの内分泌疾患と関連することがあります
尿路結石が繰り返される場合は、背後に他の疾患が隠れていないかを検査することが非常に重要です。
サプリメントやミネラルウォーターは与えてよい?
サプリメントについて
原則として、獣医師の指導なしでサプリメントを自己判断で与えるのは推奨されません。
- サプリメントに含まれるミネラル(カルシウム、マグネシウム、リンなど)やビタミンDは、結石形成に直接関与する可能性があり、結石の悪化や再発の原因になります。
- 特にカルシウムやビタミンDのサプリメントは、シュウ酸カルシウム結石のリスクを高めることが報告されています。
- 特定の栄養素が不足していると診断された場合に限り、獣医師が目的・量・期間を定めて処方することはあります(例:B6欠乏とシュウ酸カルシウム結石の関連など)。
ミネラルウォーターについて
一般的に、ミネラルウォーターは推奨されません。
- 輸入品や一部国内ブランドには硬度が高いものもあり注意が必要です。
- 水道水(日本の多くの地域で軟水)、または軟水化された浄水(硬度50以下)が基本的に安全です。
まとめ:犬の尿路結石を防ぐために避けるべき食べ物と食事管理

尿路結石は、愛犬にとっても飼い主さまにとっても悩みの種が多い病気です。一度良くなっても再発するケースが多いため、完治を目指すというよりも、「再発を防ぎながらうまく付き合っていく」病気と言えます。
その中で、もっとも重要になるのが「食事管理」と「水分補給」です。療法食は一見“味気ない”と思われがちですが、わんちゃんの健康を守るために細部まで計算されて作られたお薬と同じくらい大切なごはんです。
なかなか療法食を食べてくれないことが続いた場合は、かかりつけの獣医師に相談してください。
そして、トイレの習慣や運動、水分の摂り方、体重管理など、日々のちょっとした心がけが、再発を防ぐカギになります。
著者情報 | 獣医師監修
▼愛犬の下部尿路の健康維持に!犬猫用ゼリージュレッタ 下部尿路ケア」です。
いつものフードに添えて与えるだけで、必要な水分量を摂取できます。「チキン」「かつお」「ヤギミルク」「タイ」など、豊富なフレーバーが用意してあるので、愛犬の好みに合わせて水分補給できます。香料、保存料、人工着色料は一切使用していない無添加の安全なおやつです。
▼愛犬のおしっこが簡単に採れる!犬猫用おしっこチェックセットnyanpling®ニャンプリング
こんなワンちゃん・ネコちゃんにおすすめ
- 過去におしっこトラブルがあった
- 座ったままおしっこをするタイプ
- 病院での尿検査を受けたことがない
- 外出が苦手
- おしっこの量・回数・色・pHなどが気になっている
- 採尿をもっと手軽に行いたい
- 自宅で定期的に尿をチェックしたい
- 固まる猫砂を使っている
- 多頭飼い