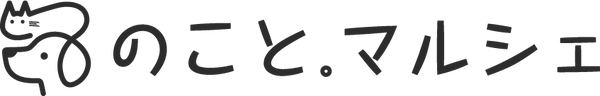「ご飯を食べないのに、手であげると食べる」──そんな愛犬の行動に戸惑っていませんか?
おやつは食べるのに主食は拒否したり、飼い主がそばにいないと食べなかったり。つい心配で手であげてしまい、やめられなくなっている方も多いでしょう。
実は、こうした行動には甘えや習慣、環境、そして体調の問題など、さまざまな背景があります。
この記事では、犬が手であげると食べる理由とやめさせ方について、獣医師の立場からくわしく解説します。愛犬が自然にごはんを食べられるようになるヒントを、一緒に探っていきましょう。
「手であげると食べる」犬の行動に隠れた5つの理由とは?

「うちの子は自分で食べず、手であげるとようやく食べる」。そんなお悩みを抱える飼い主さんは少なくありません。
この行動の背景には、甘えや習慣、食器の問題、体調不良など、さまざまな原因が考えられます。
以下で、主な5つの理由を詳しく見ていきましょう。
1. 食器や環境に対する違和感
犬は音や光、感触に敏感な動物です。個体差はあるものの、金属の器の反射や音、床の滑りやすさ、高さの合わない食器など、食事環境にちょっとしたストレスがあると、食欲が低下することがあります。
特に、食器が動く、音が響く、食べにくい高さである場合は、食べること自体をためらう原因になります。
手であげると食べる場合、「手の方が安心できる環境」と感じているのでしょう。
2. 飼い主への甘えや依存
愛犬にとって、飼い主の手は「安心」と「特別」の象徴です。食事の時間がスキンシップの延長になっていると、「自分で食べるより、飼い主にかまってもらいたい」という気持ちが優先されてしまいます。
特に、子犬期に手であげる習慣をつけてしまった場合、大人になってもそのクセが抜けず、手でしか食べない行動が固定化しやすくなります。
3. 習慣化された行動
一度「手であげると食べる」ことを覚えてしまうと、犬はそれを「ごはんをもらう正しい方法」として学習します。
その結果、器から食べることを拒否し、「手じゃないと食べない」状態が習慣として定着してしまいます。
これは、いわゆる“行動の強化”と呼ばれる現象で、意図せず飼い主が強化してしまっているケースも多く見られます。
4. 食事環境のストレス
飼い主が見ていないと食べない、他のペットが近くにいると落ち着かない、周囲が騒がしいなど、食事中の環境が落ち着かないと、犬は食欲をなくしてしまいます。
特に神経質な性格の犬や、家族の動きに敏感な犬ほど、静かな場所での食事が必要です。
5. 体調不良や痛み
最も見逃してはいけないのが「病気のサイン」です。以下の疾患などで体に不調があると、自分で食べることを避けることがあります。
- 口内炎
- 歯周病
- 胃腸障害
- 発熱
これらは一例です。この場合、「手であげればかろうじて食べる」こともありますが、体調が悪化すると、手でも食べなくなります。
いつもと違う様子があれば、早めの受診が重要です。
おやつは食べるけどご飯はイヤ?よくある3つのパターンと注意点

おやつは喜んで食べるのにご飯になるとそっぽを向く、そんな偏食傾向に悩まされている飼い主さんも多いのではないでしょうか。
これは単なる“わがまま”ではなく、習慣やフードの選び方、日々の関わり方によって生じる“学習された行動”である可能性があります。
ここでは、特に多く見られる3つのパターンと、それぞれに潜む注意点について解説します。
1. 偏食による嗜好の偏り
人間と同じように、犬にも食の好みがあります。香りの強いおやつやジャーキーなど、嗜好性の高いものを頻繁に与えていると、主食のフードへの関心が薄れてしまうことがあります。
特にトッピングを常用している場合、「フードだけでは満足できない」と犬が学習し、ご飯を拒否するようになるケースも。
これは“おやつありき”の食習慣が定着した状態で、いわば「もっと美味しいものを待っている」状態です。
注意点
嗜好性の高いおやつに慣れすぎると、総合栄養食の摂取量が減り、必要な栄養素が不足する可能性があります。食事は基本的に主食のフードから与えるようにし、おやつはあくまで「補助」として位置づけましょう。
2. ご褒美依存の食行動
「おすわりできたらおやつ」というような“報酬型の食事習慣”が長期間続くと、犬は「何か頑張らないと食べ物がもらえない」「おやつの方が価値がある」と学習してしまいます。
結果として、通常のご飯には関心を示さなくなり、条件付きでしか食べなくなるのです。
注意点
しつけの一環としての「ご褒美おやつ」は有効ですが、食事そのものが報酬になってしまうと、本来の“空腹→食べる”という自然な行動が歪みます。食事とトレーニングの目的を明確に分けて行いましょう。
3. 食事の質や提供方法のミスマッチ
与えているフードの風味や温度、粒の大きさ、または保存状態などが犬に合っていない可能性もあります。
乾燥しすぎたフードや、開封して時間が経過した酸化したフードは、嗅覚の鋭い犬にとって「美味しくないもの」と判断されやすくなります。
注意点
ごはんの温度を人肌程度に温めたり、ぬるま湯でふやかしたりすることで香りが立ち、食欲を刺激できることがあります。保存状態にも注意し、袋は密閉して冷暗所に保管するようにしましょう。
手でしか食べないとどうなる?獣医師が解説する3つのリスク

「手であげると食べるからいいや」と思っていても、それが日常化すると思わぬリスクを招くことがあります。
ここでは、犬が手からしかご飯を食べない状態が続いた場合に起こりうる3つの問題について、獣医師の視点から解説します。
1. 行動が固定化しやすくなる
犬は「こうするとご飯がもらえる」と学習すると、その行動を繰り返します。
特に「手であげる=食べる」というパターンを繰り返すうちに、「器から食べるのはおかしいこと」「手じゃないと食べたくない」と思い込んでしまいます。
こうして“手からしか食べない犬”が出来上がってしまうと、後から直すのは時間と根気が必要になります。
ポイント
これはいわゆる「条件づけ」による習慣化で、人間が知らず知らずのうちに行動を強化してしまっているパターンです。
条件付けとは、あることと嬉しいことが何回もセットで起こると、それを覚えて行動が決まってしまうことをいいます。
例①:ゲームをしたらおやつがもらえた
ある日、ゲームのあとにおやつがもらえた → 次の日ももらえた →
そうなると、「ゲームのあとにはおやつがある」と思いこんで、ゲームをもっとやりたくなってしまう
例②:犬が「手であげたら食べた」
はじめはたまたま手であげたら食べた → 次の日も手であげたらまた食べた → 何日もそうしていたら…
→ 犬は「ごはんは手でしかもらえないんだ!」と覚えてしまう
2. 飼い主の負担が増える
忙しい朝や外出前、旅行中や他人に預けるときなど、「毎回手であげないと食べない」という状況は、飼い主にとって大きなストレスになります。
さらに、他の家族やペットシッターが同じように対応できるとは限らず、「この人じゃないと食べない」といった依存的な問題にもつながります。
ポイント
飼い主にとっても犬にとっても、“自立して食べること”は健全な食生活の基本です。
3. 栄養バランスが崩れやすくなる
手であげる際、つい食べやすい部分だけを選んで与えてしまったり、柔らかいものやおやつばかり与えてしまったりする傾向があります。
その結果、総合栄養食として設計されたドライフードを十分に食べられず、ビタミンやミネラル、タンパク質の摂取が不十分になることもあります。
ポイント
特に成長期の子犬や病後の犬、シニア犬では、バランスのとれた食事が健康維持の要です。「食べてさえいれば大丈夫」とは限らない点に注意が必要です。
今日から実践!自力で食べるようになるための5つの工夫

手であげないと食べない――その習慣を変えるには、「自分で食べられる環境ときっかけづくり」が欠かせません。
無理にやめさせるのではなく、少しずつ“自立した食事”に導いてあげることが大切です。
ここでは、すぐに始められる5つの実践的な工夫をご紹介します。
1. 食器の見直し
犬の体格や食べ方に合わない食器は、食欲の妨げになります。
たとえば器が滑る、音が鳴る、角度が合っていない、首に負担がかかるなどがあると、犬は「なんとなくイヤ」と感じて器を避けるようになります。
滑り止め付きの器や、食べやすい高さの食器台を使うことで、自然と自分で食べられるようになる場合がありますので試してみましょう。
ポイント
ステンレス→陶器、浅皿→深皿、高さなし→高さありなど、いくつか試して犬の様子を観察しましょう。
2. 食事場所の見直し
テレビの音や人の動き、他のペットの存在など、食事中に気が散ると犬は落ち着いて食べられません。
静かで落ち着ける場所に器を置き、そっと見守るようにしてみてください。
飼い主の目線や声かけが逆にプレッシャーになるタイプの犬もいます。
ポイント
他の部屋に移動する、視線を避けるなど、少しの工夫で集中しやすくなります。
3. 食事時間のルールをつくる
「食べないと心配で出しっぱなしにしてしまう」というのは逆効果です。
時間を決めて器を置き、10〜15分食べなければ下げてしまった方が良いです。
それを繰り返すことで、「今食べないとごはんがなくなる」と学習し、自発的に食べるきっかけになります。
ポイント
食べなかったからといってすぐに手で与えるのではなく、「自分で食べるしかない」状況を、やさしくつくるのがコツです。
4. フードの香りと食感を工夫する
ドライフードが食べにくそうな場合は、ぬるま湯でふやかす・電子レンジで少し温める・香りの強いトッピングを少量加えるなどの方法が効果的です。
ただし、トッピングは毎回変えず、一定のルールで与えましょう(例:朝のみ、量を決めるなど)。
ポイント
与えるたびに違う工夫をすると「今日は何かな?」と期待が高まり、フードそのものを食べなくなるリスクもあります。
また、ここで食べなければもっといいトッピングが出てくるはずだという学習をしてしまうのを防ぐためにも、一定のパターン化が大切です。
▼いつものご飯にトッピングがおすすめ!愛犬の食いつきがよくなる⁉犬猫用ゼリー「ジュレッタ」です。
いつものフードに添えて与えるだけで、必要な水分量を摂取できます。「チキン」「かつお」「ヤギミルク」「タイ」など、豊富なフレーバーが用意してあるのでおいしく水分補給できます。香料、保存料、人工着色料は一切使用していない無添加の安全なおやつです。
5. 食べたらしっかり褒める
犬が自分で器から食べたときは、必ず褒めてあげましょう。
声かけやアイコンタクト、なでるなど、「自分で食べる=うれしいことがある」と教えてあげることで、行動の定着につながります。
ポイント
ご褒美にすぐおやつをあげる必要はありません。声や表情、スキンシップで十分に報酬になります。
何日食べなければ病院へ?獣医師が判断の目安を解説

「手であげればなんとか食べるけど、自分からはまったく食べない」「この状態が何日も続いていいのか不安…」
そんな不安を抱える飼い主さんは多いです。
Q:手であげれば食べるけど、自分で食べない…このまま様子を見ていいの?
A:手であげれば食べる場合、すぐに命に関わるリスクは高くない場合が多いですが、油断は禁物です。
とくに、
- 高齢犬
- 持病がある子(心臓・腎臓など)
- 子犬
- 発熱
の場合、体力の低下が早いため、2日以上続くようなら受診を検討してください。
Q:手でも食べなくなったら?
A:健康な成犬であっても、何も食べない状態が丸1日以上続くようであれば注意が必要です。
ただし、以下のようなケースでは時間に関係なく早めの受診が必要です。
- 子犬や小型犬では、12時間程度の絶食でも低血糖を起こす可能性がある
- 「食べない」ことに加えて、元気がない・水も飲まない・下痢や嘔吐があるといった症状が見られる
- 慢性疾患(心臓、腎臓、内分泌疾患など)を抱えている
|
状態 |
様子を見る期間 |
受診すべきタイミング |
|
手であげれば食べる |
1〜2日 |
長引く or 他の症状あり |
|
手でも食べない(健康な成犬) |
1日程度 |
他の症状があれば即受診 |
|
手でも食べない(子犬・小型犬) |
半日程度 |
低血糖のリスクがあるため早期受診 |
|
水も飲まない |
数時間以内 |
迷わず受診 |
この表の期間より短い期間だと受診してはいけない、というわけではありませんので、あくまでも参考にしていただければと思います。
【関連記事】猫が急にカリカリを食べない時の理由と対策を解説!ウェットフードは食べる場合も
まとめ|愛犬が自然にご飯を食べられるようにするために

「ご飯を食べないけど、手であげると食べる」──
そんな愛犬の行動には、甘え、習慣、食事環境、体調など、いくつもの背景が隠れています。
無理にやめさせようとするのではなく、原因を正しく理解し、少しずつ自力で食べられる環境へと導くことが大切です。
まずは、食器や場所の見直しから。
次に、食べる時間やフードの与え方、褒め方を整え、手であげる回数を少しずつ減らしていきましょう。
それでも改善しない場合や、「そもそも食欲が落ちている」と感じたときは、早めに獣医師へ相談をしましょう。
愛犬が「ごはんって楽しい」「自分で食べられる」と感じられるようになること。
それが、健やかな日常への第一歩です。
著者情報 | 獣医師監修